本稿では、DAOやコミュニティ財務(トレジャリー)の運用を、ステーブルコインの「デュレーション梯子(ラダー)」と、ETH/BTC等のパーペチュアル先物によるデルタ・ヘッジで組み合わせ、資金効率と可用性(流動性)を同時に高める方法を解説します。読了後には、最小限のリスクでキャッシュフローを安定化しつつ、市場変動に対して防御しやすい基本設計を自力で構築できるようになります。
1. なぜ「トレジャリー設計」が難しいのか
トレジャリー運用は、単一のKPIで最適化できません。可用性(すぐ使えるか)、安全性(価格や信用の安定性)、収益性(利回りやリベート)がしばしばトレードオフになるからです。短期の支出を見越してすべてを現金同等に置けば安全ですが、利回りは低下します。逆に長期ロックやボラ資産に寄せれば、価格変動やロールリスクが増えます。したがって、目的別の資金階層と時間分散(デュレーション)を組み合わせる設計が有効です。
2. 三層アロケーション・モデル(流動性階層)
まずは用途別に3つの層を用意します。比率は一例です。運用チームの意思決定速度や収入の季節性に応じて調整します。
- 運転資金(30%):支払やマーケ費など、直近1〜4週間で確実に使う分。原則は日次引き出し可のステーブル(例:USDC)に置きます。
- 耐久準備(50%):1〜6か月の支出に備える中期層。30/60/90日の満期ラダーや、短期金利連動のオンチェーン資産(例:短期国債トークン、期間型レンディング)を活用します。
- 成長枠(20%):長期的な価値成長・コミュニティ戦略投資。ETHやエコシステムトークンなどに限定し、ヘッジの有無と想定ボラを明確化します。
この三層により、日次キャッシュニーズと利回り確保を両立させます。
3. ステーブルコインの「デュレーション梯子(ラダー)」
ラダーは、異なる満期のポジションを等間隔で並べる方法です。例えば、30日・60日・90日を同額で持てば、毎月どこかが満期を迎え、再投資(ロール)か支出に充てられます。利点は、再投資タイミングが分散され、金利変動に対する平均化が効くことです。
例として、USDC 100万を以下のように分けます:
- 日次可動(30%=30万):即時出金可能なプール。
- 30日(30%=30万):短期ロックまたは期日型の貸付。
- 60日(20%=20万):中期。
- 90日(20%=20万):やや長め。
こうすると、毎月最低でも20〜30万USDCが満期化し、資金繰りの見通しが立てやすくなります。再投資条件(利回り・手数料・スマートコントラクトの健全性)をチェックする標準手順も用意しておきます。
4. ETHエクスポージャの「デルタ・ヘッジ」
トレジャリーがETHを保有する理由は、エコシステム整合性や長期的な成長期待があるからです。一方で、短期の予算管理にとって大きな価格変動は致命的になり得ます。そこで、先物(パーペチュアル)でショートしてデルタを抑える方法を使います。
基本式は単純です。ヘッジ枚数 ≈ スポットETH保有枚数 × ヘッジ比率。例えば、500 ETH保有で価格変動を半減したいなら、250 ETH相当を先物ショートします。ヘッジ比率はリスク許容度や資金需要に応じて0〜100%で調整します。
5. ファンディングレートとヘッジコストの見方
パーペチュアルのショートは、ファンディングレート(一定間隔の支払/受取)を伴います。年率換算は次のとおりです。
年率換算 ≈ (各間隔の資金調達率) × (年間間隔回数)例:8時間ごとに+0.01%の支払い(ショート側が支払)なら、1日3回 × 365日 ≈ 1095回です。年率はおおよそ0.0001 × 1095 ≈ 10.95%となります。ショートの維持コストとして見積もり、ラダーで稼ぐ金利(クーポンや貸付利回り)とネットで比較します。
反対に、ショートが受取になっている局面では、ヘッジコストが軽減される(あるいは利回り化する)場合があります。したがって、金利とファンディングの相対関係を常にモニターします。
6. 実務の設計:取引所・保管・権限分離
- 取引所選定(CEX/DEX):板厚・清算エンジン・追証設計・API安定性を重視します。ヘッジ用途は約定品質とダウンタイム耐性が最優先です。
- 保管(セルフ/カストディ):マルチシグやMPCを用い、運用(トレード)鍵と保管鍵を分離します。ホットの権限は最小限、コールドはしきい値署名で。
- 権限分離:フロント(執行)、リスク(限度とヘッジ比率)、カストディ(送金承認)を分け、二重承認を標準運用にします。
7. ステップ・バイ・ステップ実装手順
- 資金需要の時系列化:過去12か月の支出を週次・月次で整理し、最低必要現金同等残高を定義します。
- 三層比率の決定:例(30/50/20)。予備費の閾値(例:運転資金の2.0倍)をKPI化します。
- ラダー構築:30/60/90日に均等配分し、満期ロール日をカレンダー化。ロール条件(最小金利、スマコン健全性)をチェックリスト化。
- ETH保有方針:ヘッジ比率(例:50%)とロスカット/縮小基準(例:資金調達年率が15%超で縮小)を文書化します。
- ヘッジ実行:先物口座に担保を分離、清算価格の安全マージン(例:現値から±25%)を確保し、過度なレバレッジを避けます。
- モニタリング:ファンディング・年率、ロール予定、流動性カバレッジ(何か月分の支出を賄えるか)をダッシュボード化します。
8. ケーススタディ:100万USDC+500 ETHのトレジャリー
初期状態:
- USDC 100万(ラダー:日次30万、30日30万、60日20万、90日20万)
- スポットETH 500
- ヘッジ:先物ショート 250 ETH(ヘッジ比率50%)
想定:
- ラダー平均利回り:年率5.0%
- ファンディング年率:ショート側支払 6.0%
ネット収支はおおよそ「+5.0%(ラダー) − 3.0%(ヘッジコストの半分相当)= +2.0%」のイメージになります(ヘッジ比率や実際の資本配分に依存)。ファンディングが受取化する相場ではネットが改善します。
ショック時の動き:
- ETH急騰:スポット益が増えるがショート損が拡大。ヘッジ比率を少し落として方向性を取りに行くか、維持して予算の安定を優先するかを事前にルール化します。
- ETH急落:ショート益が出るため、運用キャッシュの安定性が増します。過剰ヘッジには注意します。
- 金利急変:ファンディング年率が想定超(例:15%)ならヘッジ比率を下げる or 満期ロールを短く再編し、ネット収支を守ります。
9. 指標とダッシュボードのKPI
- 流動性カバレッジ月数:運転資金+満期化予定で、何か月の支出を賄えるか。
- ネット金利:ラダー利回り −(ヘッジコスト × ヘッジ比率)。
- ETH実効デルタ:スポット − 先物。0に近いほど価格中立。
- ロール集中リスク:同日満期が偏っていないか。
- 清算距離:担保と清算価格の乖離率。
10. よくある失敗と対策
- ラダーの形骸化:ロール日を忘れる → カレンダー化と自動通知で回避します。
- 過度なヘッジ比率:上昇相場で機会損失 → 上限と下限(例:30〜70%)を定義し、月次で見直します。
- 清算マージン不足:担保を兼用して逼迫 → ヘッジ用担保は別口座で隔離します。
- 権限集中:単独署名で事故 → マルチシグ/MPCのしきい値を運用に組み込みます。
11. 最小構成チェックリスト
- 三層比率(運転・準備・成長)を文書化
- 30/60/90日のラダー金額を設定
- ETHヘッジ比率と調整ルールを決定
- ロール日と承認フロー(2名以上)を設定
- ダッシュボードのKPIを可視化
12. まとめ
トレジャリー運用は「使えるお金を切らさない」ことが最優先です。そのうえで、ステーブルのデュレーション分散とパーペチュアルのヘッジを組み合わせれば、価格変動の大きい市場でも資金計画を安定させつつ、手堅くネット収益を積み上げられます。まずは小さな金額で実装し、ロールとヘッジの運用ルーチンをチームに定着させましょう。

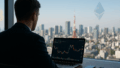

コメント