この記事は、暗号資産の先物・パーペチュアル取引やCFD・証拠金取引における「清算価格(Liquidation Price)」と「マークトゥーマーケット(Mark-to-Market, MTM)」を、初学者でも実務に落とし込めるレベルで体系的に理解できるよう構成しています。一般論の列挙ではなく、数式・数値例・Excel式・運用プロセス・チェックリストまで具体的に示します。
1. まず結論:清算を避けるための最重要原則
清算は「口座の有効証拠金 ≤ 維持証拠金」の瞬間に発生します。有効証拠金は「口座残高+含み損益(MTM評価)」で刻一刻と変動し、維持証拠金は建玉サイズと取引所のティア(段階)で決まります。ゆえに、清算は価格だけではなく、MTM評価・手数料・資金調達(Funding)・複数ポジションの相殺・モード(クロス/分離)に左右されます。
- 原則A:レバレッジを下げる(証拠金余力>>維持証拠金)
- 原則B:分離マージンで損失を限定し、致命傷を回避
- 原則C:ストップ(トレーリング含む)と枚数制御で清算前に撤退
- 原則D:Funding・手数料・スリッページを前提コストとして織り込む
- 原則E:高ボラ時は建玉を縮小、ボラ目標に合わせる(Vol Targeting)
2. 用語の基礎整理
2.1 清算価格(Liquidation Price)
取引所がポジションを強制的に解消する価格。維持証拠金を下回ると清算エンジンが作動するため、実際の発生条件は取引所の仕様(マーク価格基準、インデックス価格基準、フェア価格基準など)に依存します。
2.2 破産価格(Bankruptcy Price)
ポジションを強制解消しても証拠金がゼロになる理論価格。清算は通常、破産価格の手前で試行されます。約定できない場合は保険基金(Insurance Fund)やADL(自動デレバレッジ)が関与します。
2.3 マークトゥーマーケット(MTM, Mark Price)
ポジションの損益評価に用いる参照価格。直近約定(Last)ではなく、市場インデックスと資金調達等から導くフェア価格を使うのが一般的です。清算判定にもMark Priceが採用されることが多く、不正なラストティックによる清算を防止します。
2.4 初回証拠金 / 維持証拠金
建玉に必要な最小証拠金。レバレッジを上げるほど初回証拠金率は下がりますが、維持証拠金率(MMR)はティアに応じて下限があり、建玉が大きいほど絶対額が増加します。
2.5 クロスマージン / 分離マージン
クロスは口座全体の残高で損益を相殺し耐えるモード。分離はポジションごとに証拠金を区切り、損失を限定できます。初心者は分離推奨です。
3. 清算価格の考え方(単純化した基本式)
ロングの分離マージンを例に、費用と手数料を一旦無視した最小モデルで考えます(実運用では後述のように調整が必要)。
数量Q、建玉価格P_0、マーク価格P、名目Notional = Q·P、初回証拠金率IMR、維持証拠金率MMRとすると、分離マージン口座の有効証拠金は概ね:
Equity_isolated ≈ Deposit − Q·(P_0 − P)清算判定は、Equity_isolated ≤ MMR · Q · P を満たす最初のPです。整理するとロングの清算近似価格P_Liqは:
P_Liq ≈ (Deposit + Q·P_0) / (Q·(1 + MMR))ショートは符号が反転します。実際は手数料・Funding・価格参照(Mark)・段階別MMR・保険基金等でズレます。取引所はUI上で清算価格を動的に計算して表示しますが、概算を自分で算出し、事前に余力を確保することが重要です。
4. 具体例:BTCUSDTパーペチュアル(分離5倍)
仮定:
・口座入金(該当ポジ用の分離証拠金)= 2,000 USDT
・建玉価格 P0 = 60,000 USDT
・数量 Q = 0.1 BTC(名目 6,000 USDT)
・レバレッジ 5倍(IMR ≈ 20%)
・維持証拠金率 MMR = 0.5%(例)
概算清算価格:
P_Liq ≈ (2,000 + 0.1×60,000) / (0.1×(1+0.005))
= (2,000 + 6,000) / 0.1005
≈ 7,960 / 0.1005 ≈ 79,204 USDTこれはロングの逆方向(下落)で清算が近づくため、上式は単純化の例示です。実際はMark Price採用、手数料差引、Funding反映、ティアでのMMR変動、保険基金を考慮して取引所のUI算出と差が出ます。重要なのは、自前の保守的計算で「想定より手前で死ぬ」状況を避けることです。
※初心者は、UIに表示される清算価格+α(安全マージン)を自分の損切り価格として先に置き、清算は絶対に待たない運用に徹してください。
5. クロスと分離で何が変わるか
クロス:口座全体の残高と他ポジの評価益で耐えられる反面、悪化時は全体が巻き込まれやすい。プロはヘッジやデルタ中立で口座全体のボラを抑えた上で使います。
分離:ポジションごとに証拠金を限定でき、想定外の急変での致命傷を局所化できます。初心者は原則こちら。
清算価格は、クロスでは他ポジの評価損益・口座残高の変化で動的に遠のいたり近づいたりします。分離は固定的で読みやすい反面、証拠金が尽きれば即清算。使い分けの基準は「想定外の連鎖損失を避けたいなら分離、ポジション間の相関を設計し全体最適を図れるならクロス」です。
6. MTM(Mark Price)と清算の関係
MTMは評価に用いる基準価格で、清算トリガーにも使われやすい価格です。多くの取引所は、指数価格+ベーシス調整(資金調達・金利差・先物ベーシス)でMark Priceを算出します。
- メリット:ラストティックの異常値で清算しにくい
- 留意点:指数構成やベーシス計算は取引所ごとに仕様差、イベント時は指数遅延や乖離も起こる
初心者ほど「利確/損切り/トリガーはMark Price基準」の注文を選び、UIのトリガー種類(Mark/Last/Index)を毎回確認してください。
7. Funding(資金調達)・手数料・スリッページの埋伏リスク
Fundingは定期的に残高に加減算され、クロスの耐久力や分離のEquityを動かします。高い正のFundingを払い続けるロングは、清算価格が実質的に近づく点を見落としがちです。手数料・スリッページもEquityを蝕みます。
運用ルール:
- ポジション開始前に「1日あたりの想定Fundingコスト」を年率化し、許容ホールド期間内で総コストを見積もる
- 想定スリッページ×往復回数+手数料を固定費として前計上
- コスト累計で清算ラインが手前に来る前提で余力を厚くする
8. 清算を遠ざける7つの実践策
8.1 建玉サイズ=口座の1〜2%リスクを上限に
損切り位置までの損失額が口座残高の1〜2%以内に収まるよう数量を逆算します。清算を前提にせず、清算前に損切る設計にします。
8.2 レバレッジは必要最低限に
ボラが高い銘柄ほど低レバで足りる。目安として、日中ボラ(%)×レバレッジが10%を超えるようなら危険域です。
8.3 分離マージン+余剰を厚めに
分離で致命傷を避けつつ、証拠金は必要額+30〜50%を常に余剰として置く運用を推奨。
8.4 事前に逆指値(Mark基準)を設置
「清算まで待つ」は破綻の王道。トリガーはMark Price、執行タイプは市場成行(またはIOC)で滑っても逃げる。
8.5 高Funding・イベント前は縮小/クローズ
高い正のFundingを払い続けるロング、重要指標・雇用統計・FOMC等の直前はサイズを半減または一旦フラットに。
8.6 ヘッジ(先物・オプション)を使う
ロングの下押し懸念に対し短期のプット買い、ショートに対してコール買い(ストラングル/ストラドル併用)で尾リスクを抑制。
8.7 ボラ目標運用(Vol Targeting)
過去N日の実現ボラでサイズを調整し、口座ボラを一定に保つ。極端な高ボラ時は自動的に建玉が縮む仕組みを自ら作る。
9. ケーススタディ(実務寄り)
ケースA:BTCロング、Fundingコストで首が締まる
ロング0.5BTC、分離、清算余力十分。しかし年率30%相当のFundingを支払い続け、2週間で口座のEquityが5%減少。価格は横ばいなのに清算価格が相対的に近づいた——Funding放置は緩慢な「清算接近装置」です。
ケースB:ETHショート、指数乖離で一瞬ヒヤリ
イベント急騰時、現物指数の構成取引所の遅延でMark Priceが跳ね、ショートの清算ラインに接近。指数の仕様・バックアップ指数を事前に把握しておくべきでした。
ケースC:クロス運用の連鎖
複数ペアをクロスで保有し、片方の急変で口座全体のEquityが減少。相関を誤読すると耐久力が一気に削れる。クロスは設計者向けです。
10. Excel / Google Sheets 実装(初心者の最低限)
以下は分離ロングの安全側概算。セル参照は例です。
# 入力
B2: Deposit(証拠金)
B3: Quantity(数量Q)
B4: Entry(P0)
B5: MMR(維持証拠金率) 例: 0.005
B6: FeeRoundTrip(往復手数料・滑り想定)
B7: FundingPerDay(1日あたりの想定)
B8: HoldDays(予定保有日数)
# 清算近似(費用考慮の安全側)
B10: = (B2 - B6 - B7*B8 + B3*B4) / (B3*(1 + B5))
# 逆指値(清算のx%手前)
B11: = B10 * (1 + 0.02) # 2%手前で撤退など実務では、取引所UIが示す清算価格よりさらに手前に逆指値を置きます。テスト時は小口で検証し、滑り・手数料・Fundingの実測を反映して式をチューニングしてください。
11. よくある誤解と対策
- 「清算価格は固定」— Fundingや手数料でEquityが動けば相対的に近づく。UIの値も動的。
- 「ラスト価格で清算される」— 多くはMark基準。トリガー種類を確認。
- 「クロスは安全」— 相関崩壊で全体が巻き込まれる。設計できないなら分離。
- 「高レバでもストップがあるから大丈夫」— 滑りでストップ飛ばし→即清算の危険。
- 「イベントはチャンス」— 指数乖離・流動性枯渇・スプレッド拡大を織り込む。
- 「Fundingは誤差」— 水平相場でも口座を削る。長期保有は禁物。
- 「手数料は小さい」— スキャルで往復を重ねるほど効く。メイカー/テイカー差も計算。
- 「清算で全部ゼロ」— 保険基金・ADLの関与で結果は前後するが、ゼロ前に逃げる設計が基本。
- 「オプションは難しい」— プット買いのシンプルな保険から始める。
- 「サイズは感覚」— 1〜2%ルールとボラ目標で機械化する。
12. ミニ辞典(最低限おさえる用語)
- Mark Price(MTM)
- 評価に用いる基準価格。清算トリガーにも。
- Bankruptcy Price
- 強制解消後に証拠金がゼロとなる理論価格。
- MMR(維持証拠金率)
- 建玉維持に必要な最低証拠金率。ティアで増加。
- クロス/分離
- 口座全体で相殺するか、ポジションごとに区切るか。
- ADL
- 自動デレバレッジ。保険基金で吸収しきれないときに発動。
- Funding
- パーペチュアル特有の資金調達。ロング/ショートの片側が支払う。
13. 運用プロセス(テンプレ)
- 想定シナリオと損切り価格を先に決める(清算ではなく)。
- 1〜2%ルールで数量逆算、分離で証拠金を割当。
- 逆指値(Mark基準・成行)を同時に設置。
- Funding・手数料・滑りの前計上。
- イベント前は縮小、実現ボラが閾値超なら自動縮小。
- 日次でEquity・清算距離・Funding累計を点検。
- 想定外の連続ギャップ時は全クローズを躊躇しない。
14. まとめ:清算は「結果」、防ぐのは「設計」
清算を避ける最短経路は、レバを下げ、分離で損失を限定し、逆指値で撤退し、コストを見積もり、ボラでサイズを調整すること。清算ラインからの逆算ではなく、損切り位置とリスク上限から数量を機械的に決める習慣が、長期の生存率を決めます。


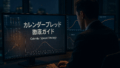
コメント