レバレッジは利益も損失も増幅します。本稿では「清算(強制ロスカット)」の数式を起点に、初学者でも実務で使える安全域(Safety Margin)の設計手順を徹底解説します。対象は暗号資産の証拠金取引(先物・パーペチュアル/USDT建て・インバース建て)です。抽象論は排し、具体例と計算式、チェックリストまで落とし込みます。
前提整理:証拠金・レバレッジ・維持証拠金
初期証拠金(IM)はポジションを建てるのに必要な最低額、維持証拠金(MM)はポジションを維持するために必要な最低額です。口座残高−含み損がMMを下回ると清算が発動します。多くの取引所では段階的MM(ポジション規模が大きいほどMM率が上がる)が採用されています。
清算価格の基本式(USDT建て・分離マージン・ロング)
代表的な約定・損益計算を簡略化したモデルで示します(手数料・資金調達・価格乖離は一旦無視)。数量Q(BTC)、建玉価格P0(USDT)、レバレッジL、初期証拠金IM=Q·P0/L、維持証拠金率m(例:0.5%)とすると、ロングの清算価格Pliqは概ね:
P_liq ≈ P_0 · (1 − 1/L + m)
例:P0=60,000、L=10、m=0.005 → P_liq ≈ 60,000 · (1 − 0.1 + 0.005) = 54,300 USDT
ショートは符号が逆:
P_liq ≈ P_0 · (1 + 1/L − m)
クロスマージンの注意
クロスでは口座の未使用証拠金全体が緩衝材として使われ、清算価格は口座総資産と未実現損益で動きます。分離に比べ式は固定できず、「口座有効資産 ÷ ポジション名目」が実効レバレッジを決めます。安全運用では分離を基本にし、必要時のみクロスに切り替えるのが無難です。
インバース契約(コイン建て)の直感
インバースでは損益がコイン建てで計算され、USDT建てとは感度が逆転する場面があります。ロングの含み損はQ·(1/P − 1/P_0)(BTC建て)で増減し、価格が半分になると損失は非線形に膨らみます。初心者はまずUSDT建てで安定運用し、インバースはヘッジ用途に限定すると管理が容易です。
安全域(Safety Margin)を数値で設計する
清算を避ける設計は次の3ステップで完結します。
- ボラの把握:対象銘柄の日次標準偏差σを過去N=60〜90営業日で推定。初心者は簡易にATR(14)を代用可。
- 許容損失の決定:1トレードの最大損失(例:口座の0.5%)を先に決め、そこから許容ポジション規模Qを逆算。
- 清算価格のバッファ設定:直近の最大1日変動幅(例:3σ、またはATRの2倍)を清算価格までの距離より小さくしない。
数学的には、ロングで
P_0 − P_liq ≥ k · σ · P_0(k=2〜3)
を満たすようにLを下げる(またはQを縮小)します。
サイズの決め方(固定リスク方式)
口座残高E、許容損失率r(例0.5%)、ストップ幅Δ(%)とすると、USDT建てロングの名目サイズNは:
N = (E · r) / Δ
必要証拠金はN/L、数量QはN / P_0。清算価格がストップ価格より内側に来ないよう、先に清算価格を計算してから発注します。
実例:BTCUSDT パーペチュアル
前提:口座1万USDT、許容損失0.5%(50USDT)、エントリーP0=60,000、ストップは−0.6%(Δ=0.006)。
- 名目サイズ N = 10,000×0.005/0.006 ≈ 8,333 USDT
- 数量 Q ≈ 0.1389 BTC
- L=5倍なら必要証拠金 ≈ 1,667 USDT
- m=0.5%のとき Pliq ≈ 60,000·(1−0.2+0.005)=48,300(清算距離19.5%)
ストップ幅0.6%に対し清算距離19.5%で十分なバッファ。もし清算距離が短いなら、レバレッジを下げる/サイズを落とすのが正解です。
資金調達(Funding)・手数料の影響
パーペチュアルでは資金調達支払が長期保有の敵になります。年率換算で+5%を超える環境では、短期回転かヘッジ(先物・現物)を検討。手数料(taker/maker)は往復で0.06%前後でも高頻度売買では効きます。期待値は:
期待値 ≈ 勝率·平均利益 − (1−勝率)·平均損失 − コスト(手数料+資金調達)
勝率・損益R・取引頻度を前提に、コストが期待値を食い潰していないか毎月点検しましょう。
ボラティリティ・ターゲティング(口座全体の安定化)
日次目標ボラσ*(例:1%)を決め、前日実現ボラσに応じて次回の名目Nをスケール:
N_t = N_{base} · (σ_* / max(σ, ε))
荒れ相場では自動的にサイズが縮小し、清算確率を下げます。裁量でも「直近のATRが閾値を超えたら倍率0.5」などの簡便ルールで代替可能です。
逆指値・OCO・追跡ストップの実務
清算回避の第一手段は早めの損切り。発注と同時にOCO注文(利確指値+損切り逆指値)を置き、値幅は最初に決めたΔに一致させます。トレンドフォローなら追跡ストップ(trailing)で利を伸ばし、平均損益R>1を徹底します。
ギャップ・スリッページ・端数
急変時は逆指値が滑り、想定より悪い価格で約定します。清算価格とストップ価格の距離を十分に取る理由がここです。最小価格刻み・最小数量の制約で端数が出た場合は、ストップを刻み値に合わせて調整します。
ブラックスワンへの備え
停電・回線断・取引所障害は定期的に起こります。対策は:(1)分離マージン+低レバレッジ、(2)サイズを口座の一部に限定、(3)API障害時の緊急手順(スマホ回線・代替取引所)を用意。
よくある失敗と対処
- 逆指値を置かない:即改善。新規同時OCOを標準化。
- 清算価格を見ていない:発注前チェックリストに清算距離≥3σを追加。
- 実効レバの過大化:クロス+未実現損で気づかない。分離基本に戻す。
- 段階MMの見落とし:サイズが増えるほどMM率が上がる。分割エントリーで管理。
発注前チェックリスト
- 清算価格(取引所計算機)と自計算の値が概ね一致
- 清算距離 ≥ 3σ または ATR×2
- OCO同時設定(損切り逆指値は価格刻みに適合)
- 想定コスト(手数料+資金調達)を期待値で吸収可能
- 口座全体の有効レバ <= 2倍(初心者の目安)
簡易テンプレ(手書きでOK)
毎トレードで以下を埋めるだけで劇的に事故が減ります。
銘柄:________ 方向:Long/Short 口座残高E:____USDT 許容損失r:____% エントリーP0:____ ストップ幅Δ:____% 名目N:____USDT 数量Q:____ 予定レバL:____倍 想定清算P_liq:____ 清算距離:(P0−P_liq)/P0=____% 資金調達想定:____年率 取引コスト往復:____% OCO設定:Yes/No 代替回線・取引所:準備OK/要確認
まとめ
マージントレードで勝ち続けるコツは、「清算を前提にしない」ことではなく、「清算が理論的に遠い構造を先に作ってから建てる」ことです。清算価格の式を出発点に、サイズ・レバ・ストップ・コスト・ボラの順で制御すれば、初心者でも事故率を大幅に下げられます。まずは分離・低レバ・固定リスク方式で小さく始め、記録を取りながら改善してください。
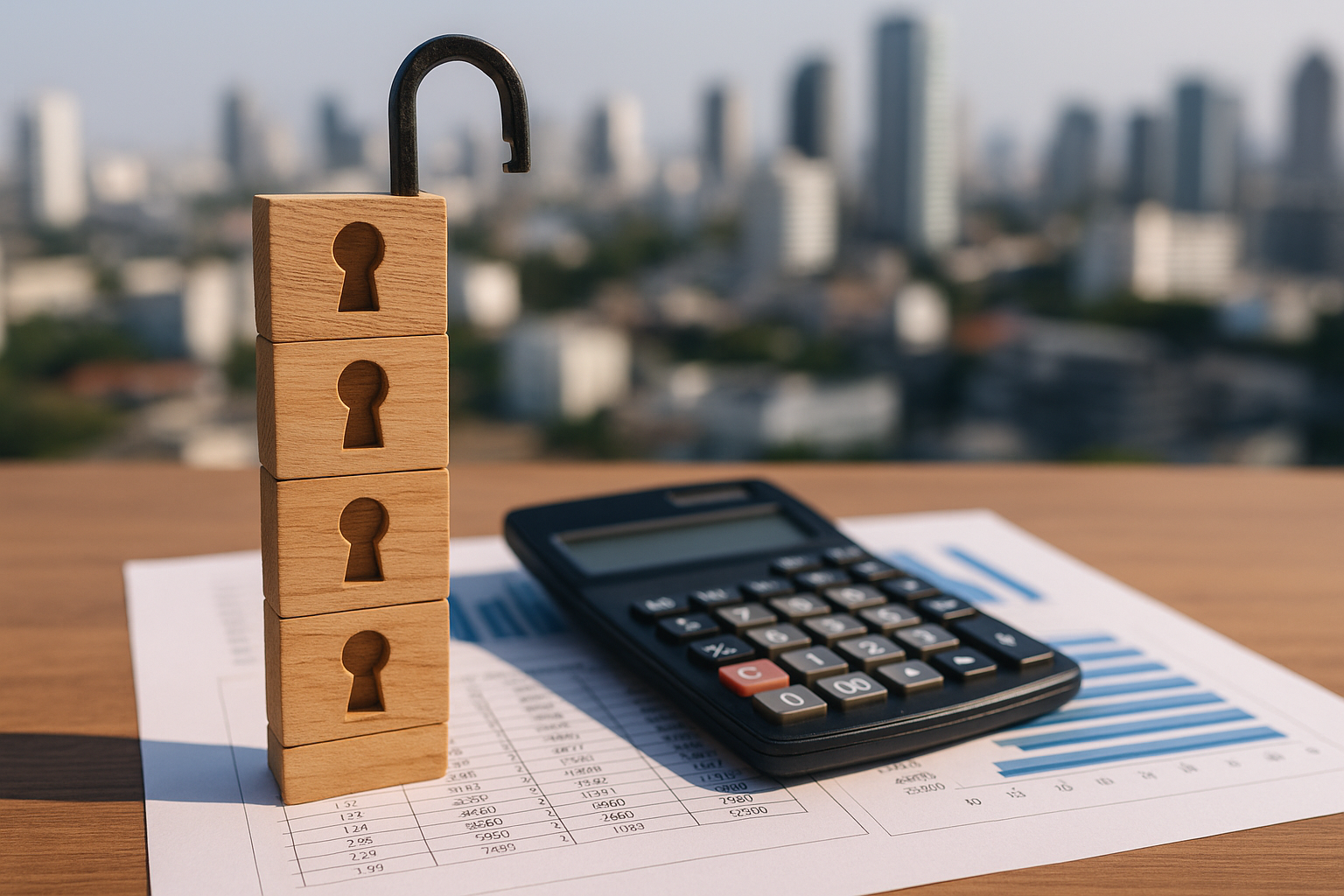
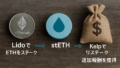

コメント