「価格が上がるか下がるか」に賭けないで、資金調達率(Funding Rate)そのものを継続的なキャッシュフローとして狙う——それが無方向性ベーシス戦略です。パーペチュアル先物(以下、パーペチュアル)は現物価格に連動させるために、建玉残高の偏りに応じて定期的に資金授受を行います。強気相場ではロングが支払い/ショートが受け取りになりやすく、逆相場ではその反対になります。本稿では、現物と先物を同時に持ってデルタ(価格変動感応度)を極小化しながら、資金調達率を回収する実務を、手順と数値で整理します。
資金調達率の仕組みと前提
パーペチュアルは満期がない代わりに、一定間隔(例:8時間ごとや4時間ごと)で建玉間の資金授受を行い、インデックス価格に近づけます。多くのUSDT建ての線形契約では、資金調達率 × 建玉名目が支払額/受取額の基礎になります。マーク価格(清算に用いられる価格)とインデックス価格の乖離や、資金調達率の上限/下限、予測値の表示タイミングは取引所によって細部が異なります。
基本形:現物ロング+パーペチュアルショート
強気地合いでロング超過が続く局面では、資金調達率がプラスに張り付くことが多く、ショート側が受け取り手になります。ここで現物を同額ロングしておくと、価格上昇による先物ショートの評価損は現物の評価益で相殺され、方向性の影響を抑えつつ、純粋に資金調達の受取が残ります。
建玉設計(USDT線形契約の例)
口座残高10,000 USDT、BTC価格=50,000 USDT、資金調達率=+0.01%/8hとします。
(1) 現物:0.2 BTC(=10,000 USDT相当)を購入。
(2) 先物:BTCUSDTパーペチュアルを名目10,000 USDT分ショート(クロスではなく分離推奨)。
(3) 期中の価格変動で評価損益は動くが、理論上はデルタほぼ中立。8時間ごとにショート側が10,000×0.0001=1 USDTを受け取る想定。
年率換算の考え方
1回あたりの受取=名目×資金調達率。1日3回なら日次=名目×資金調達率×3。単利年率(目安)=日次×365。
上記の例では日次=1×3=3 USDT、年率目安=3×365=1,095 USDT(≒10.95%/年)。もちろん実際の資金調達率は変動し、手数料・スリッページ・資本コストで目減りします。
実務コストと“見落としがちな摩擦”
手数料:メイカー/テイカー手数料、先物の資金調達と別に約定時のフィーが発生します。リベートやVIP階層は収益性に直結。
スリッページ:現物と先物を同時に建てるほど有利。板の厚みが薄い時間帯は不利。
資本コスト:現物側のUSDTやフィアット調達コスト、円転・出金手数料。
清算リスク:先物側は証拠金維持が必須。分離マージン+余裕の維持率でADL(自動デレバレッジ)と清算を回避。
資金調達反転リスク:短期でマイナスに反転すると支払い側に。
指数構成とオラクル:インデックスの構成や障害時の代替ルールを確認。
先物の種類:USDT線形とUSD建てインバースで資金調達の計算式やヘッジ比率が変わる点に注意。
数値で見る損益分解
例:名目100,000 USDT、資金調達率+0.02%/8h、手数料合計(往復)=0.02%、スリッページ=0.01%、証拠金コスト=年2%相当と仮定。
・初回構築コスト=(手数料+スリッページ)×名目=0.03%×100,000=30 USDT。
・日次受取期待=100,000×0.0002×3=60 USDT。
・年率換算粗利=60×365=21,900 USDT。
・資本コスト控除(2%)=2,000 USDT。
・理論純益(ボラなし想定)=21,900−2,000−初期コスト30≒19,870 USDT。
もちろん資金調達率が低下すれば期待値は下がります。成立するかは「資金調達の持続×規模」≧「摩擦とリスク」で決まります。
執行フロー(最小可動の手順)
(1) 取引所の資金調達率・予測値・決済時刻を確認(銘柄ごとに異なる)。
(2) 建玉名目を決定(口座余力、清算価格、許容乖離を逆算)。
(3) 現物ロング→先物ショートをできるだけ同時に約定。
(4) 決済タイミング前後のポジション乖離を点検(価格急変・スプレッド拡大時)。
(5) 目標利回り/損益に応じて縮小・撤退。
(6) 収益と手数料の別集計(税務・監査対応のため)。
撤退条件と再投入ルール
・資金調達率の3回連続低下や、0%近傍の滞留。
・取引所の保全ファンド(保険基金)の急減や、ADL頻発。
・ボラテリティ急上昇で乖離が拡大し、ヘッジ誤差が大きい。
・手数料優遇階層が落ち、純受取が閾値を割る。
撤退後は閾値(例:+0.01%/8h超×n銘柄)で再スキャン、分散投入。
逆張り版:資金調達マイナスの回収
弱気相場で資金調達率がマイナスに張り付くと、ロング側が受け取りになります。ここでは先物ロング+現物ショートが基本形。ただし現物の空売りコスト(レンディング手数料)や調達の難度が増し、板の借り不足がボトルネックになります。代替として、同一取引所の貸借機能や他銘柄での疑似ショート(相関ヘッジ)を検討します。
DEXパーペチュアルでの注意点
GMXやPerpetual Protocol、DriftなどのDEXでは、資金調達はLPプールの需給・オラクルに依存します。清算と価格参照がCEXと異なり、ガス代・遅延・オラクル更新間隔が収益に影響します。ウォレット管理(ハードウェア/マルチシグ/MPC)とブリッジのセキュリティも別軸のリスクとして加わります。
モニタリング設計
ダッシュボードに並べると良い指標:
・各銘柄の資金調達実績/予測(直近n回の移動平均)。
・スプレッド・板の厚み・建玉急増。
・保険基金残高・ADL発動件数。
・清算価格までの距離・証拠金率。
・ポジション乖離(現物と先物の名目差)。
よくある落とし穴
・資金調達“だけ”を信じる:相場転換で反転し、支払い側に回る。
・過剰レバ:清算→ヘッジ崩壊で想定外の損失。
・指数障害:バックアップルール未確認。
・税務未整理:資金調達受取の区分・計上タイミングが曖昧。
・カウンターパーティ:取引所障害や出金停止のリスク分散不足。
発展:分散と最適化
・銘柄分散:BTC/ETHに加え、資金調達が継続して偏りやすいアルトを薄く分散。
・取引所分散:障害・規約変更リスクを軽減。
・閾値最適化:予測資金調達×持続確率×ロット−摩擦>0 で自動発注。
・期間分散:決済タイミングがずれる銘柄で階段状に保有し、イベント集中リスクを平準化。
まとめ
無方向性ベーシスは、「資金調達の偏り」を源泉にした運用です。鍵は、(1)デルタ中立の精度、(2)摩擦の最小化、(3)反転に備える撤退ルール。この3点を機械的に守れる体制を作れれば、相場の上下と関係なく再現性の高い収益源になり得ます。最初は小さな名目でプロセスを固め、監視と記録のルーチンを完成させてから規模を上げるのが安全です。
※本稿は情報提供のみを目的とし、特定の取引の勧誘ではありません。手数料・税務・規約は各自で最新の一次情報をご確認ください。

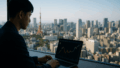

コメント