本記事では、投資初心者でも実務ですぐに役立つように、マークトゥーマーケット(Mark-to-Market, MTM/値洗い)の仕組みと活用法を徹底解説します。先物・CFD・暗号資産パーペチュアル(無期限先物)・FX差金決済など、日々価格が動き、証拠金が刻々と変化するプロダクトでは、MTMの理解が勝敗を分けます。含み益・含み損の考え方、証拠金率・レバレッジ・清算価格(ロスカット)との関係、日次清算や資金調達料(Funding)の影響、ロールオーバー時の価格調整金など、初歩から実戦まで具体例で解説します。
MTM(値洗い)とは何か
MTMとは、保有ポジションを「取得価格(簿価)」ではなく「現在の公正価値(時価)」で評価し、損益や証拠金を日々(あるいは取引時間中に連続的に)更新する仕組みです。株式の現物投資では含み損益を眺めるだけでも済みますが、先物やCFD、暗号資産の無期限先物、証拠金取引(マージン取引)では、MTMに基づく評価が資金管理の中核になります。理由は単純で、時価評価によって「今この瞬間にどれほどの損益が出ており、どの程度の余力が残っているか」がロスカット判定や追証(マージンコール)に直結するからです。
なぜMTMが重要なのか:3つの観点
1. リスク制御の土台
MTMはボラティリティと連動して証拠金余力を揺さぶります。評価損が拡大すると余力が縮み、清算価格に接近します。逆に含み益は余力を押し上げます。したがって、MTMは損切り水準やトレーリングストップ、ポジションサイズの調整など、リスク制御ロジックの土台です。
2. 資金フローの可視化
先物取引所では日次清算(Variation Margin)が行われ、評価益は口座に振り込まれ、評価損は差し引かれます。暗号資産無期限先物では資金調達料(Funding)によりロングとショート間で定期的な支払いが発生します。CFDでは日々の金利調整やロールオーバーの価格調整金が資金フローを変えます。MTM理解はこれらのキャッシュフローを読み解く鍵です。
3. 成績評価と戦略改善
MTMベースで日次のリターンを集計することで、シャープレシオ、最大ドローダウン、VAR相当指標などが測定可能になります。これにより、戦略の改善が「勘」ではなくデータドリブンに進みます。
アセット別:MTMの仕組みとクセ
先物(取引所取引)
代表例は株価指数先物や国債先物、商品先物です。原則として日次清算が行われ、取引終了時点(Settlement Price)で評価損益が確定し、口座残高が更新されます。必要証拠金は「初回(Initial)」「維持(Maintenance)」に分かれ、日次清算で維持水準を割ると追証が発生します。単位あたり損益は「(清算価格 − 建値)× 乗数 × 枚数」で算定されます。
CFD(店頭デリバティブ)
CFDは証拠金とMTMの発想は先物と同様ですが、指数やコモディティの期近から期先への乗り換え(ロールオーバー)時に「価格調整金」が動きます。これは「先物の期近と期先の理論差(コンタンゴ/バックワーデーション)」を反映する調整で、MTM上の損益とは別軸のキャッシュフローです。ロールの瞬間に建値が切り替わるため、表面上は“マイナスの価格調整金”でも、乗り換え後の新限月での値動きと合算でトータル損益は整合的になります。
暗号資産・無期限先物(Perpetual Swap)
無期限先物では「マーク価格(指数現物ベースの公正価格)」に基づいて未実現損益と清算判定が行われます。清算価格は、証拠金、レバレッジ、手数料、Funding の影響を受けます。Funding は8時間ごと等の頻度で発生することが多く、MTMの損益とは別にキャッシュフローが発生します。未実現損益は概ね「(マーク価格 − 平均建値)× 契約数 × 乗数(USDT建てなら名目に依存)」で近似されます。
MTMの基本計算式と用語整理
未実現損益(UPnL):UPnL =(マーク価格 − 平均建値)× 契約数量 × 乗数
実現損益(RPnL):クローズ時点の価格で確定。先物では日次清算でRPnL化する場合もある。
有効証拠金(Equity):口座残高 + UPnL − 手数料 − Funding 等
証拠金率(Margin Ratio):必要証拠金 ÷ 有効証拠金。一定閾値超過でロスカット。
レバレッジ(Leverage):名目(ポジション価値)÷ 有効証拠金。UPnLで動的に変化。
清算価格(近似):ロングの場合、清算価格 ≒ 平均建値 − (初期証拠金 − 手数料調整)÷(契約数量 × 乗数)。取引所ごとに厳密式は異なるため、実際はプラットフォームの提示値を必ず確認します。
ケーススタディ:日次の値洗いを数字で追う
ケース1:株価指数先物(1枚、乗数¥1,000)を日次清算
前提:平均建値=¥33,000、有効証拠金=¥1,500,000、維持証拠金=¥500,000。
1日目の清算価格=¥33,300 → UPnL=+¥300×1,000=+¥300,000。日次清算でRPnL化、口座残高が増える。
2日目の清算価格=¥32,900 → 当日損益=−¥400×1,000=−¥400,000。残高から差し引かれ、維持証拠金割れなら追証。
結論:先物では「毎日確定」するため、勝っている日は資金が増え、負けている日は減る。含み損益に酔わず、日次のキャッシュフローで管理する。
ケース2:暗号資産・BTC無期限先物(USDT建て、クロスマージン)
前提:平均建値=USDT 60,000、数量=0.5 BTC、マーク価格=59,400、乗数=1(USDT建て)。
UPnL = (59,400 − 60,000) × 0.5 = −USDT 300。
8時間ごとに Funding=+0.01% とする(ロング受取)。名目=59,400×0.5=USDT 29,700 → 受取=USDT 2.97。
Equity は UPnL と Funding の和で微調整される。清算価格はプラットフォーム提示値に従うが、概ねマーク価格が下がるほど接近する。Funding はMTMの損益と別レイヤーで資金移動することに注意。
ケース3:指数CFDのロールオーバー(価格調整金)とMTM
前提:S&P500指数CFDの期近から期先へ乗り換え。期先が期近より高いコンタンゴ。
ロール時、保有ロングに「マイナスの価格調整金」が発生することがある。これは「期先が割高」の分だけ理論上の逆ザヤを調整するもので、MTMの含み益・損とは別のキャッシュフロー。
翌日以降、期先の価格水準でMTMが続くため、トータル損益は「価格調整金+その後の値動き」で決まる。ロール瞬間の調整だけを切り取って悲観(あるいは楽観)しないこと。
よくある誤解と破綻パターン
- 含み益を担保にポジションを拡大しすぎる:UPnLは変動する。ボラ急拡大で一気に逆回転し、清算連鎖に陥る。
- マーク価格ではなく最新約定で損益を見てしまう:清算判定は多くのプラットフォームで「マーク価格」基準。油断は禁物。
- ロールオーバーの調整金を損だと誤解:理論上は先物カーブの形状に沿った再配分。トータルで評価する。
- クロスマージンでの複数ポジション干渉を軽視:1銘柄の損が他の余力を吸う。分離マージンやヘッジで火事延焼を防ぐ。
- Fundingの方向を勘違い:ロング優勢相場ではロングが支払いになりがち。逆に弱気相場ではショートが支払い。都度確認。
実務チェックリスト(毎日・毎週・イベント前)
毎日
- マーク価格ベースのUPnLと清算価格までのバッファ(%)を確認
- 証拠金率・レバレッジの自動警報(閾値アラート)
- Funding・金利調整・手数料のスケジュール確認
毎週
- 日次リターンの分布、ボラ、最大ドローダウンを更新
- ポジションとキャッシュの相関(相関が高いヘッジ不全に注意)
イベント前(指標・決算・ロール)
- サイズ削減(Position Sizing)とトレーリングストップの見直し
- ロール時の先物カーブ(コンタンゴ/バック)を確認し、必要なら一時スクエア化
戦略にどう活かすか
1. トレーリングストップとMTMの連携
UPnLが一定比率に達したらストップ水準を引き上げる「利益のロック」をMTMで自動化。清算価格との距離も監視し、余力の過大消耗を回避します。
2. スプレッド取引の日次評価
期近ショート+期先ロングなどのカレンダースプレッドでは、レッグごとにUPnLを算定し、合算でのボラを抑える。先物カーブの傾きが収斂・拡大する局面をデータで把握。
3. VAR相当の簡易リスク上限
過去n日の日次損益分布から「95%分位の損失額」を上限として、名目やレバレッジを調整。MTMの時系列がVARの材料になる。
ミニツール:MTMと証拠金率の簡易ロジック(MQL4)
// 未実現損益と証拠金率の簡易計算(CFD/先物風の概念)
double CalcUPnL(double markPrice, double avgPrice, double qty, double multiplier){
return (markPrice - avgPrice) * qty * multiplier;
}
double MarginRatio(double equity, double requiredMargin){
if(requiredMargin <= 0) return 0;
return requiredMargin / equity; // 1.0超で危険域のイメージ
}
// 清算価格の粗い近似(ロング): 実運用では取引所提示値に必ず従うこと
double ApproxLiqPriceLong(double avgPrice, double equity, double qty, double multiplier){
if(qty*multiplier<=0) return 0;
return avgPrice - (equity)/(qty*multiplier);
}
※上記は概念確認用の擬似コードです。実際の取引所は手数料・Funding・保険基金・フェアプライス調整等を考慮した固有式を採用します。清算価格は常にプラットフォームの提示値を優先してください。
数字で腹落ちさせる:ワークトレーニング
- 任意の銘柄で「平均建値・数量・乗数・マーク価格」をExcelに入力し、UPnLとEquityを毎日更新。
- レバレッジと清算価格(近似)を同時算出し、「清算までの距離(%)」を可視化。
- Funding・金利・ロールのイベントを別列で管理し、MTM損益と非価格要因の資金移動を分けて集計。
まとめ:MTMは“数字で負けない”ための共通言語
MTMは、相場観の当たり外れ以前に「資金が尽きないように戦う」ための最低条件です。未実現損益、証拠金率、清算価格、Funding、ロール調整金。これらを同じ物差し(時価評価)で一元管理することで、無駄な破綻リスクを劇的に減らせます。まずは小さく実装し、日次のMTMから資金フローの感覚を身体に刻み込みましょう。


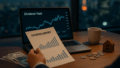
コメント