異なるオプションを組み合わせる戦略です。典型的には「短期を売り・長期を買う」ロング・カレンダーを用います。
目的は時間価値(セータ)とインプライド・ボラティリティ(IV)の構造を収穫し、価格が大きく
動かない局面で安定的な損益曲線(テント型)を作ることにあります。本稿は初学者でも実装できるよう、概念→設計→発注→管理→撤退まで
手順を一気通貫で解説します。
1. 戦略の骨子:何を狙うのか
ロング・カレンダーは「近い期限の時間価値の減少が速い」「期限が長いほどIVに敏感」という市場の性質を同時に利用します。
具体的には、短期オプションを売って時間価値を受け取り、長期オプションを買って将来のIV上昇を取りに行く
構造です。ベースとなる相場観は「大きなトレンドは出にくい(レンジ)」「ただしイベントでIVは上がる可能性がある」という状況。
価格が期近満期に向けて権利行使価格付近に留まると損益のピークに近づきます。
2. 仕組みとギリシャ指標
ロング・カレンダー(期近を売り・期先を買い・同一ストライク)の一般的なギリシャは以下です。
- セータ(Theta):概ねプラス。期近売りの時間価値減少が期先買いを上回るため。
- ベガ(Vega):プラス。期先買いの方が期間が長く、IV上昇で有利。
- ガンマ(Gamma):マイナス。価格の急変に弱く、テントの外側で損益が悪化。
- デルタ(Delta):構築直後は小さく、価格変動に対して中立に近い。
要するに「時間は味方・IV上昇は追い風・急激な値動きは逆風」という性質です。
3. どんな相場で機能しやすいか
下記の条件が複数重なるほど期待値が安定します。
- 基礎資産がレンジ相場で推移しやすい(モメンタムが弱い)。
- イベント(決算、指標、政策発表など)の前に期近を売り、イベント跨ぎは期先側に温存できる設計。
- オプション市場の流動性が十分(板が厚い、スプレッドが狭い)。
- IVの期限構造(Term Structure)とスマイルが素直(極端な歪みが少ない)。
4. 構築レシピ:ストライクと満期の決め方
教科書的な基本は「同一ストライク・期近売り/期先買い」です。初回はATM(アット・ザ・マネー)を推奨。
ATMはテントのピークを現在価格付近に置けるため、期近満期まで価格が大きく動かなければ最も効率が良い構造になります。
満期は、期近14〜45日・期先45〜90日の組み合わせが扱いやすいレンジです。
応用として「ダイアゴナル・カレンダー(期先のストライクをややOTMにずらす)」があります。
たとえば「将来的にやや上昇を見込む」なら、期先はややOTMコールを買い、期近はATMまたはややITMを売ると、デルタをわずかに
強気寄りに調整できます(弱気ならプット側)。
5. 具体的な数値例(すべて仮定)
銘柄ABC、現値100。IVは期近が22%、期先が24%とします。次のようなロング・カレンダーを構築。
買い:コール 100ストライク 60日満期 価格 3.80 売り:コール 100ストライク 30日満期 価格 2.10 ネットデビット(支払い)= 3.80 - 2.10 = 1.70
期近満期(30日後)の概算損益イメージ:
- ABCが100付近:売りコールは時間価値の減少でほぼ消滅、買いコールは30日残存の時間価値を保持。利益のピークに近い。
- 大きく上昇(110など):売りコールが実質的にITMで消滅せず、買いコールの内在価値は増えるが、ガンマ負けで利益は限定的。
- 大きく下落(90など):両コールの価値が共に低下。ネットデビット分に対し損失拡大。
最大利益は「期近満期時に原資産がストライクに近い」ほど大きくなり、理論上は期先の残存時間価値の山が利益源。
最大損失は原則として支払ったデビット(本例なら1.70)にほぼ限定されます(取引コスト除く)。
6. 入口チェックリスト(実務)
注文前に以下を確認してください。
- 流動性:対象銘柄のオプションに十分な出来高があり、板のスプレッドが狭いか。
- イベント把握:決算・指標・政策会合・配当落ち日など。期近は跨がない設計が無難。
- IV期限構造:期先IV ≧ 期近IV が望ましい。少なくとも期先が大きく劣後しないこと。
- ストライク:基本はATM。相場観がある場合のみダイアゴナルでわずかに傾ける。
- サイズ:1スプレッドから開始し、価格行き過ぎ時の追加(分割エントリー)余力を残す。
7. 管理とローリング(期近の更新)
期近満期が近づいたら、以下の分岐で意思決定します。
- 価格がテント内(±3〜5%程度)→ 期近を買い戻して翌期近を再度売る(ローリング)。
これを繰り返し、期先が“母屋”として収益基盤になります。 - 上に抜けた→ 期近を買い戻し、より高いストライクの期近を売る(ダイアゴナル化)。
強いトレンドなら一旦クローズで損失限定も選択。 - 下に抜けた→ 期近を買い戻し、低いストライクの期近を売る(プット側に切り替える手も)。
ローリングは「時間価値の収穫を再投資する」作業です。過剰に回数を増やすより、広がったテントを保つ感覚で
低コスト・低ストレスに続ける方が成績は安定しやすいです。
8. 代表的な失敗パターンと対策
失敗はパターン化できます。典型例と対処を挙げます。
- イベント後のIVクラッシュ:決算跨ぎで期先IVが下落。→ イベント手前で期近を売り切る設計にし、
期先IVの下落に備えてサイズを抑える。必要なら一度クローズ。 - トレンド発生でテント外へ:ガンマ負け。→ ダイアゴナル化・垂直スプレッドへの転換・クローズで損失限定。
- 流動性不足:板が薄くスリッページ拡大。→ 銘柄選定の時点で回避。指数や大型株・主要ETFに限定。
- 配当・早期権利行使の誤算:アメリカン型コールの早期行使は配当が主因。→ 配当落ち日前は期近売りを回避・早めに買い戻す。
9. 手仕舞いの基準
以下のいずれかで撤退を検討します。
- 含み益の目標到達:ネットデビットの50〜80%を確保できたら利益確定。
- 価格がテント幅を逸脱:テクニカルに±1ATR〜1.5ATRを超えたら撤退または構造変更。
- IV環境の悪化:期先IVの優位が消滅、または板が急に薄くなった場合。
10. 応用編:ダブル・カレンダーとカレンダー⇄バタフライ転換
ダブル・カレンダーはコールとプットの両側で同時にカレンダーを組む手法。レンジ予想が強く、IV上昇を
幅広く取りたいときに有効です。強い方向性が出た場合は負け側を畳み、勝ち側をダイアゴナル化します。
また、期近がATM付近で減価していく場面では、カレンダーをバタフライへ転換(長い期先を部分的に利確し、
期近の売りを増やしてテントを鋭くする)ことで、短期間に利益を凝縮できる局面もあります。
11. コストと実務ディテール
約定コスト、取引所手数料、為替、金利、証拠金(ブローカー規約)を必ず事前に把握してください。短期で何度もローリングするほど
コストは複利で効いてきます。1回あたりのスリッページを最小化し、回転率を上げすぎないことが実務の肝です。
12. まとめ:カレンダーは「時間」を武器化する
ロング・カレンダーは、時間価値の収穫(+セータ)とIV上昇(+ベガ)を同時に取りに行く、レンジ局面向けの戦略です。
流動性がある指数・大型株・主要ETFで、イベント日程と期限構造を踏まえて設計すれば、初心者でも段階的に運用を学べます。
「大きく動かなければ不利になりにくい」わけではありません。急変に弱い(−ガンマ)ため、管理と撤退が成否を分けます。
本稿のレシピ(入口チェック、ローリング、失敗パターン対策)を作業手順として定着させてください。
付録:簡易シミュレーションの考え方
ブラック–ショールズやバリアントを使った厳密計算が理想ですが、実務では「期近は時間で消え、期先は残る」という直感を
可視化できれば充分に役立ちます。証券会社のリスクグラフ機能で、建玉の損益図を「本日」「期近満期前日」「期近満期当日」の
3枚で比較してください。ピークがストライク上に形成され、外れるほど損益が落ちる“テント型”が見えるはずです。


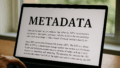
コメント