バタフライスプレッドは、一定の価格帯に「着地」する確率に賭けて、リスクを限定しながら高いリスクリワードを狙うオプション戦略です。レンジ相場やイベント前後のボラティリティ変化を捉えるのに適しており、限月・権利行使価格(ストライク)・構成比率を微調整することで、想定レンジに対して鋭い利益ピーク(テント型の損益曲線)を設計できます。本記事ではロング/ショートのバタフライ、アイアン・バタフライ、ブロークンウィング(非対称)までをカバーし、損益式・ギリシャ指標・具体的数値例・執行ノウハウ・調整シナリオ・撤退ルールを実務レベルで解説します。
要点は次の3つです。第一に、バタフライは「想定中心価格(ミドル・ストライク)に収束するほど利益が最大化」されます。第二に、ロング構成は損失限定のデビット型、アイアンや一部のブロークン構成はクレジット型で時間価値を取りに行く設計が可能です。第三に、ギリシャ指標の設計により、イベント前後のインプライド・ボラティリティ(IV)の低下から利益を得たり、狭いレンジを想定してガンマの山を「狙い撃ち」できることです。
- 1. バタフライの基本構造を最速で理解する
- 2. 損益式・最大損益・損益分岐点
- 3. ギリシャ指標の設計思想
- 4. 数値例①:株価100の銘柄に対するロング・コール・バタフライ
- 5. アイアン・バタフライ(クレジット型)
- 6. ブロークンウィング・バタフライ(非対称で“保険”を安く買う)
- 7. どんな相場で機能するか(ユースケース)
- 8. IVの読み方とストライク選定(1σ設計と実務の近道)
- 9. 執行の具体論(板取り、手数料、スリッページ)
- 10. 調整(アジャスト)の型
- 11. リスク管理(サイズ・分散・相関)
- 12. 事例研究:イベント後の「IVクラッシュ+レンジ」狙い
- 13. 暗号資産での活用(欧州型・24/7・板の深さ)
- 14. FX・金利での応用(参考)
- 15. シンプルな検証アイデア(手作業でも再現可能)
- 16. 仕掛け前チェックリスト(保存版)
- 17. よくある質問
- 18. 付録:簡易損益計算の作り方
- 19. まとめ
- 20. ストライク選定の数学的直観(確率密度とテントの重ね合わせ)
- 21. ガンマ・スカルピングとの併用
- 22. P/L感度表の例(概念図)
- 23. 初心者向け練習メニュー(4週間)
- 24. よくある失敗と回避策
- 25. 事例研究②:BTC週次での実装イメージ
- 26. 実践フローチャート(仕掛け→管理→手仕舞い)
1. バタフライの基本構造を最速で理解する
最も基本的なロング・コール・バタフライは、以下の4枚のポジションで構成します。
- 低いストライクK1のコールを1枚買い
- 中心ストライクK2のコールを2枚売り
- 高いストライクK3のコールを1枚買い(K1 < K2 < K3、通常は等間隔)
ネットでプレミアムを支払う「デビット」構成が一般的です。満期時の損益は、原資産価格SがK2付近で最大利益、K1以下やK3以上に乖離すると損失は支払ったネット・プレミアムに限定されます。プットを用いても同様の形状を作れますが、実務では流動性と建玉コストに応じてコール版・プット版を選びます。
一方、ショート・バタフライは逆にネットで受け取り(クレジット)から始まり、中心から離れた動きに強く、中心に留まると損失が拡大する設計です。初心者はまずロング構成から着手し、損失限定のフレームで訓練するほうが安全です。
2. 損益式・最大損益・損益分岐点
等間隔(K1=K2−d、K3=K2+d)のロング・コール・バタフライ(1:−2:1)の満期損益(デビット型)の直感は次の通りです。
- 最大利益(Max Profit)… ミドルK2にピン留めされたときに理論上最大。概念的には「ストライク間隔 d × 1枚分 − ネットデビット」。
- 最大損失(Max Loss)… 支払ったネット・プレミアムに限定。
- 損益分岐(BE)… 概ね「K1+ネットデビット」および「K3−ネットデビット」(コール版の近似)。厳密にはプレミアム配分で若干ずれます。
ポイントは、幅(d)を広げるほど最大利益の“理論上限”は増えますが、中心にピン留めされる難易度も上がることです。実務では「想定レンジ」×「約定コスト(スプレッド・手数料)」×「IV変化」を同時に満たす幅をチューニングします。
3. ギリシャ指標の設計思想
ロング・バタフライは、中心付近でおおむねデルタ中立に近づき、ガンマは中心付近でピーク、シータは時間経過と共にプラスに転じやすく(特にアイアン構成や近い期日)、ベガはマイナスになりやすい性質があります。要するに「中心に近づく小さな価格変動」や「IVの縮小」から利益を得やすいのが特徴です。逆に大きくトレンドが発生し、中心から外れる動きやIV急騰には弱くなります。
ガンマピークは「精密さの裏返し」です。中心近傍を当てたときの利益密度は高い一方、外すと時間価値の効果が希薄化します。したがって、中心ストライクの選定とイベント・カタリストの読みが重要です。
4. 数値例①:株価100の銘柄に対するロング・コール・バタフライ
想定:現値S=100、等間隔幅d=5、K1=95、K2=100、K3=105、満期まで14日。市場のオプション価格から次のようなプレミアムが観測されたと仮定します。
- 95Cを+1枚 = 支払 2.30
- 100Cを−2枚 = 受取 2×1.20 = 2.40
- 105Cを+1枚 = 支払 0.65
ネット・デビット=2.30 − 2.40 + 0.65 = 0.55(1枚あたり)。手数料は簡略化のため一旦ゼロとします。損益分岐の目安は下側が95+0.55=95.55、上側が105−0.55=104.45です。最大利益の理論上限は幅d=5からデビット0.55を引いて概ね4.45(満期かつピン時)となります。
シナリオ解像度を上げるため、3つのパスを比較します。
- パスA(理想):満期時にS=100。最大に近い利益4.45前後が実現します。
- パスB(レンジ内):S=103。利益はピークから低下しますが、まだプラス圏(概算で2~3程度)です。
- パスC(外れ):S=107。K3超えで価値が薄くなり、損失はデビット0.55に近づきます。
この例の含意は明確です。中心付近に着地するほど報酬は非線形に跳ね上がり、外れるほど損失は一定に抑えられるという非対称性が、ロング・バタフライの魅力になります。
5. アイアン・バタフライ(クレジット型)
アイアン・バタフライは、中心ストライクでショート・ストラドル(コール売り+プット売り)を構成し、外側にプロテクティブな買い(コール買い+プット買い)を付けるクレジット戦略です。満期時に中心付近で最も利益が大きく、外側への逸脱では損失がウィングにより限定されます。時間価値(シータ)が味方になりやすく、「動かない」相場を売る思想に近いですが、ウィングで尾部リスクを限定できるのが大きな利点です。
実務の勘所は、中心ストライクの選び方とウィング幅のバランスです。中心を現在値にジャストで合わせると利益ピークは高くなりますが、わずかなブレで損益が劣化します。やや外した中心(±0.3~0.5σ)に設定して、片側に重みを持たせる設計も現実的です。
6. ブロークンウィング・バタフライ(非対称で“保険”を安く買う)
ブロークンウィングは片側のウィングを遠ざけて非対称にし、ネット・クレジットにする、あるいは保険コストを抑える設計です。例えば、下落をやや厚くガードしつつ、上方向の利益ピークを狙う構成などが可能です。相場の「歪み」(IVスキュー)を利用し、右肩の保険を安く、左肩を厚くといった設計にすると、実質コストゼロ〜小さな受け取りでテントを建てられることがあります。
注意点は、非対称化により「遠い側」のガードが薄くなることです。ギャップで想定外に飛ばれた場合の最大損失を必ず事前に把握し、サイズを調整します。ブロークンは便利ですが、設計を誤ると「見えない穴」ができます。
7. どんな相場で機能するか(ユースケース)
典型例は以下の通りです。
- 決算・イベント後のレンジ化:ビッグイベント後にIVが低下しやすく、価格も一服する見込みのとき、ロング・バタフライやアイアン構成で「中心付近の滞留」と「IV縮小」を同時に取りに行きます。
- ボックス相場の売買:テクニカルに明確なレンジ(支持・抵抗)が見えている場合、中心をボックス中央か、ややオーバーシュートを想定した位置に置きます。
- 指値的な発想:バタフライは「特定価格に来たら利益が大きい」という性格から、狙い価格への指値+時間価値を同時に組み込むイメージで使えます。
- 資金効率の最適化:現物や先物の代替として「ピン時の報酬密度」を上げたい場合に、限られた資金で高いRR比を設計できます。
逆に、強トレンドやボラティリティ急騰の局面では不利になりやすいので、イベントの方向性が読みにくいときはサイズを抑えるか、ブロークン化やヘッジを併用します。
8. IVの読み方とストライク選定(1σ設計と実務の近道)
現場では、満期までの「インプライド1日当たり変動幅」や「満期時の1σ期待レンジ」を基準に、ウィング幅dと中心K2を決めます。実務の近道は次の手順です。
- 対象のIVと日数から、満期までの期待変動幅(例:±5%)を概算する。
- 中心K2を現値±0~0.5σに設定。イベント方向に偏りを感じるなら、中心をわずかに寄せる。
- ウィング幅dは0.6~1.0σを起点に、板の厚みと約定しやすさで微調整。
- 中値(mid)からの約定歩み値(例:mid−0.01〜0.03)を前提に、ネットデビット/クレジットを更新して損益分岐を再計算。
「美しい理論形状」より「実際に約定してスケールできること」を優先します。スプレッドが広い銘柄では、等間隔を少し崩しても約定性を取るほうが、実収益は安定します。
9. 執行の具体論(板取り、手数料、スリッページ)
4レッグのスプレッドは単発の指値では填まりにくいため、ストラテジー発注(コンボ注文)を使って同時約定を狙います。約定率を上げるコツは以下です。
- まずミドルのショート2枚を基準に net mid を把握し、そこから±数ティックで提示して交渉する。
- 出来高とオープン・インタレストが厚い限月・ストライクに寄せる。多少の理論値劣化より約定性を優先。
- ロットを分割して段階的に建てる。テントを複数本に分ける感覚で。
- 手数料込みの損益分岐を常に再計算する。特に小さなデビットの戦略では、手数料がRRを大きく毀損します。
米株のアメリカン型オプションでは、配当や金利要因で早期行使・割当(アサイン)リスクが出ます。満期前にインザマネー化して時間価値が小さくなると、逆算的に行使が有利になる局面があるため、ショート側の管理を徹底します。一方、欧州型(指数や一部の暗号資産)の場合は満期決済のみでアサインは原則ありません。
10. 調整(アジャスト)の型
外したときの標準手順を決めておくと、主観で迷いにくくなります。
- 時間での撤退:満期まで残り日数が半減したら、一度RRを再評価して不要なら撤退。ピーク付近にいないのにシータ狙いで保有を続けるのは非効率です。
- 価格での撤退:中心から±0.8〜1.0σを超えたら基本撤退。ガンマの効果が消え、戻り待ちは期待値が悪化します。
- BWB化:反対側のウィングを遠ざけてブロークンにし、ネット受け取りへ寄せる。外れ方向の損失勾配を緩める効果。
- コンドル化:中心の−2を−1にして、新たな外側で−1を追加する(ストライクをずらしてレンジを広げる)。報酬ピークは下がるが許容レンジを広げられます。
11. リスク管理(サイズ・分散・相関)
最大損失が限定といっても、サイズの積み上げで資金は毀損します。1案件あたりの最大損失許容(例:口座資産の0.5~1.0%)を定め、複数銘柄・複数限月・複数中心の分散で「テント群」を構築します。指数・個別株・暗号資産の相関が高い局面では、テールで同時被弾しやすいため、同方向のショート・ボラ集約になっていないかを点検します。
損切りは「時間」と「価格」の両軸でルール化します。特に外れたときは、希望的観測での放置が最悪です。撤退も戦略の一部です。
12. 事例研究:イベント後の「IVクラッシュ+レンジ」狙い
仮に、決算発表が終わってギャップアップした後、価格は落ち着き、IVが急低下する局面を想定します。ここで「アイアン・バタフライ(クレジット)」を、中心を現値付近、ウィングを±0.7σに設定して仕掛けます。時間経過とともにショートの時間価値が減少し、価格が中心付近に留まれば最大利益に近づきます。逆に、翌日以降にもう一段のトレンドが出たら、早めに撤退またはブロークン化でのリスク緩和を行います。
13. 暗号資産での活用(欧州型・24/7・板の深さ)
暗号資産の多くは欧州型のキャッシュ決済で、アサインが原則ありません。週次・月次限月が多く、24/7でIVが変化するため、週末のIV低下やイベント通過後のレンジ停滞を狙ったロング/アイアン構成が有効です。板が薄いアルトではスプレッドが広がりやすいため、ビットコインやイーサリアムなど流動性の厚い銘柄から始めるのが無難です。
14. FX・金利での応用(参考)
店頭の通貨オプションや金利オプションでもバタフライの思想は同じです。IVスキューやテールの厚みは通貨ペアで異なるため、相場構造に合わせてブロークン化の方向を選びます。金利イベント前後のレンジ狙いでは、期近でテントを建ててシータを厚く取り、方向性に偏りがあるなら中心をややオフセットします。
15. シンプルな検証アイデア(手作業でも再現可能)
過去データでの概念検証は、以下の型で十分実用的です。
- 対象を流動性の高い指数や大型株、BTC/ETHに限定。
- 毎週同じ曜日に、現値±0~0.5σ中心、ウィング±0.7~1.0σでロング・バタフライを建てる。
- 保有は満期−2〜0営業日まで。価格が中心へ接近したら利益確定、外れたら時間・価格ルールで撤退。
- 手数料・スリッページを現実的に加算(例:片道0.02~0.05、レッグ数分)。
集計指標は、勝率・平均RR・最大ドローダウン・月次の損益分布・相関の高い週のクラスター分析です。負け方(外れたときの挙動)を先に把握し、サイズを落とす週を決めておくと、実運用のストレスが大幅に減ります。
16. 仕掛け前チェックリスト(保存版)
- この戦略の根拠は「レンジ化」か「IV低下」か、あるいは両方か。
- 中心の選定根拠は何か(現値、±0.3〜0.5σ、テクニカル水準、ギャップ埋め等)。
- ウィング幅は板厚と約定性に最適化されているか。
- ネット・デビット/クレジットと損益分岐は、手数料込みで期待値があるか。
- 時間・価格の撤退ルールは事前に固定したか。
- アサイン・ギャップ・ニュースのテールに耐えられるサイズか。
- 同時に建てる他戦略との相関・重複リスクはないか。
17. よくある質問
Q1:ロングとアイアンはどちらが良いですか?
A:時間価値を取りに行くならアイアン、ピン狙いの非線形報酬を重視するならロングです。板や手数料を含む総コストで選びます。
Q2:中心から外れたら粘るべき?
A:原則は撤退。戻り待ちは期待値が下がりやすいです。残存日数・IV・テクニカルを総合してBWB化やコンドル化を検討します。
Q3:どのくらいの資金規模から始めるべき?
A:各市場の最小レッグコストと手数料で決まります。まずは試験的サイズでルール運用を固め、慣れてから段階的にロットを増やします。
Q4:イベント前は仕掛けますか?
A:方向性が読めないときは避けるか、ブロークン化でテールを抑えます。イベント後のIVクラッシュを取りに行くほうが初学者には扱いやすいです。
18. 付録:簡易損益計算の作り方
ロング・コール・バタフライの満期損益(1:−2:1、等間隔)を単純化して概算するには、各レッグの満期内在価値からネット・プレミアムを引き、手数料を差し引けば良いです。途中時点では、IVと残存日数が絡むため、ブラック–ショールズ等で時価評価が必要ですが、実務では表計算で十分に管理できます。
また、プロファイルの「幅 d」を変えてシミュレーションすると、ピーク利益と当たりにくさのトレードオフが視覚的に掴めます。最終的には、当てにいく幅と取れる約定の折衷点が収益の核になります。
19. まとめ
バタフライスプレッドは「価格がどこに落ち着くか」を高精度で当てにいく戦略です。損失限定の安心感と、ピン留め時の高い報酬密度が魅力であり、IV低下やレンジ停滞といった相場の癖を味方につけられます。重要なのは、中心の位置取り、ウィング幅、手数料込みのRR、そして時間・価格の撤退ルールです。これらを定型化すれば、初心者でも再現性のある収益曲線を作ることができます。まずは小さいサイズでテントを“建てる”練習を始めてください。
20. ストライク選定の数学的直観(確率密度とテントの重ね合わせ)
等間隔のバタフライは、線形片の重ね合わせでテント形状を作ります。価格の確率密度が「中心で高く、端で低い」なら、テントの中心に質量(確率)が集まり、平均的には利益が積み上がります。実務ではブラック–ショールズのリスク中立確率ではなく、実世界の帰属確率(トレンドや需給)を勘案する必要があります。テクニカルや需給イベントで、その週・その銘柄の分布が尖っている(クルトーシス高め)と判断できるなら、バタフライの優位性は増します。
IVスマイル/スキューは、コール側・プット側の価格付けの歪みを生み、バタフライのネットコストに効いてきます。スキューが強い市場では、より高い側の保険を安く買えて、非対称のブロークン設計が有利になりやすいです。
21. ガンマ・スカルピングとの併用
中心付近に価格が来て保有期間が数日ある場合、少量の現物(あるいは先物)でデルタ調整を行い、小刻みな往復で利益を積む手法があります。ロング・バタフライは中心でガンマが高いため、価格が行き来するとデルタが発生しては消えます。これを少量・高頻度で中和していくと、バタフライ単体より総利益が増えることがあります。ただし取引回数が増え、手数料・スリッページの管理が重要になります。
22. P/L感度表の例(概念図)
実務では、中心K2に対して価格が−1.2σ〜+1.2σのグリッド、時間は満期までの残存日数を数段階に区切り、(価格×時間)の二次元でP/L感度を表にします。外れ方向での損失速度、中心滞留時の時間価値の積み上がり、IVの±10〜20%変動でのP/L変化を並べておくと、高温域=撤退領域を事前に可視化できます。
23. 初心者向け練習メニュー(4週間)
- Week1:板の厚い指数(またはBTC/ETH)で、期近の等間隔ロング・バタフライを1ロットだけ試す。中心は現値近辺。約定方法に慣れる。
- Week2:中心を±0.3〜0.5σにずらしたケースを試し、ピンの難易度と利益ピークの変化を体感する。
- Week3:アイアン構成を1回だけ。時間価値の減衰と、外れたときの撤退感覚を掴む。
- Week4:ブロークン化でネット・クレジット化を試す。非対称の危険箇所を確認し、サイズ規律を固める。
24. よくある失敗と回避策
- 板が薄い銘柄で理想形状を追いすぎる:少し崩してでも約定性と手数料総額を優先します。
- 撤退が遅れる:中心から離れたら“祈らない”。時間・価格のルールを先に紙に書いておきます。
- イベント誤読:ポジション前に「想定外の2次イベント」の有無を洗い出します。指数再編、配当、追加発表など。
- サイズ過大:最大損失が限定でも、同方向の案件を積むと相関で同時被弾します。案件ごとの上限%と同時保有数の上限を決めます。
25. 事例研究②:BTC週次での実装イメージ
想定:金曜日満期の週次で、週頭にIVがやや高止まり。オンチェーンやフローから大きな方向性イベントは薄いと判断。現値を中心に±0.8σでウィングを置いたロング・コール・バタフライをネット・デビットで建てます。週中で価格が中心付近に滞留し、IVが徐々に低下。木曜までにプレミアムの半分以上を回収できたら、満期を待たずに利益確定します。逆に火水で中心から大きく外れたら、BWB化でネットクレジット寄せの再設計、またはいったん撤退して翌週に組み直します。
26. 実践フローチャート(仕掛け→管理→手仕舞い)
①相場観(レンジ/IV低下)→ ②中心・幅の仮設定 → ③板厚・約定性で調整 → ④手数料込み損益分岐の確認 → ⑤サイズ決定 → ⑥発注(コンボ)→ ⑦価格・時間・IVの3軸でモニタ → ⑧ルール一致で利益確定 or 撤退 → ⑨記録・改善点の抽出。これをテンプレ化して毎回同じ手順で回すことで、主観のブレを抑えられます。

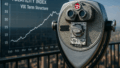

コメント