結論:カレンダースプレッド(以下「カレンダー」)は、「時間の経過(タイムディケイ)と限月間のボラティリティ構造」を収益源にするデビット型のオプション戦略です。少額のプレミアムで建てられ、値動きが「想定レンジ」に収まるほど有利に働きます。初心者でも学習コストに対してリスクが限定的で、勝ち筋が視覚化しやすいのが長所です。
本稿は、完全初心者でも今から使えるように、仕組み→勝ち筋→建て方→管理→出口の順で徹底解説します。株式・ETF・仮想通貨(例:BTC オプション)でも考え方は同じです。テクニカルの型・イベント戦略・具体例・数式の近似・チェックリストまで1本でカバーします。
- 1. カレンダースプレッドとは
- 2. 勝ち筋の輪郭:いつ・なぜ機能するのか
- 3. ギリシャの性質(長期ロング・短期ショートのカレンダー)
- 4. どんな相場で使う?(実務の当てはめ)
- 5. 具体例(数値で理解する)
- 6. IVイベントの応用(期近IVと期先IVの関係)
- 7. 建て方(手順を最短化)
- 8. 損益の感覚を“数で”掴む(簡易シミュレーション)
- 9. 代表的なアレンジ:ディアゴナル(対角)
- 10. リスク管理(ここを外すと負ける)
- 11. 出口・ロール戦略
- 12. 典型的な失敗と回避策
- 13. 数式の直観(ざっくりでOK)
- 14. テクニカル×カレンダー:入口の型
- 15. 初回の練習メニュー(具体)
- 16. ミニQ&A
- 17. チェックリスト(発注前の最終確認)
- 18. まとめ
1. カレンダースプレッドとは
同じ権利種別・同じ権利行使価格(ストライク)で、期近のオプションを売り(ショート)、期先のオプションを買う(ロング)組み合わせです。代表例は「ATMのコール・カレンダー(期近ショート・期先ロング)」です。ポジションはネットでデビット(支払い)になるのが通常で、最大損失は支払ったプレミアムがほぼ上限です。
直感的には、「近い期限の時間価値が早く減り、遠い期限の時間価値はゆっくり減る」という性質(θの差)を使って、時間の経過=味方にする戦略です。さらに、限月間のIV(インプライド・ボラティリティ)の差(タームストラクチャ)からも利益機会が生まれます。
2. 勝ち筋の輪郭:いつ・なぜ機能するのか
カレンダーが最も機能するのは、原資産がストライク付近で小さく推移し、かつ期近IVが低下 or 期先IVが相対的に維持される局面です。理由は以下の3点です。
- 時間価値の差(θの差):期近の時間価値は早く減り、期先はゆっくり減るため、「売っている期近の減りが早い=利益」になりやすい。
- IVの再均衡:イベント通過や需給の正常化で、期近IVが下がる一方、期先IVは相対的に維持されれば、ネットのベガ・エクスポージャーがプラスでもスプレッドの価値は上昇しやすい。
- 価格の中心化:ストライク付近に収束すると、期近ショートの時間価値が最も減り、ポジションの理論価値がピークに近づきやすい。
この3要素が同時に起こる「決算・マクロイベント前後の平常化フェーズ」や「トレンドが一服してレンジ化しやすい局面」で威力を発揮します。
3. ギリシャの性質(長期ロング・短期ショートのカレンダー)
- デルタ:ATM付近では概ね小さめ(≈0)。強いトレンドになるとデルタが増え、想定外方向では不利。
- ガンマ:概ねマイナス。急騰・急落の加速には弱い。レンジ相場で有利。
- セータ(θ):プラスに働きやすい。時間価値の差が収益源。
- ベガ:ネットでプラスになりやすい(期先ロングが効く)。IV上昇や期近IV低下・期先IV維持が追い風。
要するに、「大きく走らない見立て」+「イベント後のIV低下/平常化」が重なるほど勝率が高まる設計です。
4. どんな相場で使う?(実務の当てはめ)
- 材料出尽くし後の落ち着き:イベントで期近IVが高止まり→通過後に低下見込み。
- レンジ移行の初期:トレンドが一服。ボラがやや縮む見込み。
- テクニカルで“滞留価格”に接近:出来高の厚い価格帯(POC/VWAP/過去高出来高ゾーン)。
逆に、強トレンドの初動やボラティリティ拡大の連鎖(窓・急騰急落が続く)局面は不向きです。
5. 具体例(数値で理解する)
原資産価格S=100、ATMコールのIVと価格が以下だとします(概算)。
- 期近(残存30日)ATMコール:IV=28%、理論価格=3.20
- 期先(残存60日)ATMコール:IV=26%、理論価格=5.60
期近を売り、期先を買いで、ネットのデビットは 5.60−3.20= 2.40。これがほぼ最大損失です。
30日後(期近満期日)にSがちょうど100(ATM)なら、期近ショートはほぼ時間価値ゼロで満期消滅。一方、期先は残存30日となり、同じIV=26%なら理論価格はおよそ3.10〜3.40の範囲(仮)。よってスプレッド価値≈3.25前後。建玉時のデビット2.40との差≈+0.85が概算利益です。
逆にSが大きく動いて90や110へ外すと、ATM性が薄れ時間価値が落ちるため、スプレッド価値は低下し、利益は縮む・損失に転じます。これが「レンジで勝ち、走ると負ける」構造です。
6. IVイベントの応用(期近IVと期先IVの関係)
鍵は「どちらの限月にイベントが乗っているか」です。
- イベントが期近に集中:期近IV↑・期先IV→。高い期近IVを売って、相対的に低い期先IVを買う=王道のロング・カレンダー。イベント通過で期近IV↓が期待でき、時間経過と合わせて優位。
- イベントが期先に集中:期先IV↑・期近IV→。この場合は純粋なカレンダーだと期先IV低下のリスクを抱える。選択肢は(a)対角(ディアゴナル)でデルタを取りに行く、(b)イベント分を跨がない限月を選び直す、(c)スプレッド幅を狭くしてデビットを抑える。
初心者はまず「期近にイベント、期先は平常」の型から練習するのが安全です。
7. 建て方(手順を最短化)
- 原資産を選ぶ:出来高の多い銘柄やETF・主要仮想通貨(BTCなど)。
- ストライクを決める:基本はATM(現在値付近)。「やや上」ならコール、「やや下」ならプット。
- 限月を決める:期近30±10日/期先60±20日が目安。最初は1:1でOK。
- 約定の順番:同時(スプレッド注文)を推奨。板が薄い銘柄は特に。
- 約定価格の管理:デビット総額を記録(最大損失の把握)。
ブローカーのスプレッド発注画面で「カレンダー」を選び、ストライクと2つの限月を指定すれば一括で注文できます。
8. 損益の感覚を“数で”掴む(簡易シミュレーション)
以下は期近満期日における概算イメージです(前掲の設定を踏襲)。
- S=97〜103:プラス域が広い中心帯。最大利益はS=100付近。
- S=95や105:利益は縮小、ややプラス〜小幅マイナス。
- S=90や110:損失寄り。おおむねデビットに近づく。
なお、IV変化が寄与します。期近IVが通過で強く低下し、期先IVが維持されると、同じSでもスプレッド価値は増えやすい=利益が押し上がります。
9. 代表的なアレンジ:ディアゴナル(対角)
ディアゴナルは、ストライクをずらすカレンダーです(例:期近ショートをややOTM、期先ロングをATM)。軽い方向性(デルタ)を取りに行けます。緩やかなトレンド+ボラ低下を見込む局面で使い分けると、カレンダーより収益上限が広くなる一方、管理は少し難易度が上がります。
10. リスク管理(ここを外すと負ける)
- 想定外の走りに弱い(ガンマ−):大陽線・大陰線が続くと厳しい。ニュースフローとトレンド指標(移動平均・ADXなど)で回避。
- イベントの位置:どの限月にイベントが乗るかを必ず確認。期先に大型イベントが載る場合はサイズを落とすか、ディアゴナルでデルタを調整。
- 損切りライン:デビットの30〜50%で機械的に撤退を推奨(初心者)。
- サイズ規律:1回の建玉で口座の1〜2%のリスクに抑える。
- 時間の置き方:期近満期の3〜5営業日前までに概ね方向性が見える。期限いっぱいまで粘らない。
11. 出口・ロール戦略
- 利益確定の目安:デビットの30〜60%の含み益で分割利確。中心付近でのIV低下が効いたら速やかに。
- 期近が溶けたらロール:期近が十分減価し価値が薄いなら、次の期近を新規ショートして“擬似ロール”。
- 想定外の走り:早め撤退。対角化してデルタを取る選択肢もあるが、初心者は無理に追わない。
12. 典型的な失敗と回避策
- イベント配置の見落とし:限月ごとのカレンダーに必ずイベントを書き込む。どちらに決算・FOMC等が載るか。
- 薄い板で約定コストが嵩む:主要ETF・大型銘柄・主要暗号資産で練習する。
- 満期直前まで粘る:ガンマ・ギャップの餌食。3〜5営業日前に判断するルール化。
- サイズ過多:連敗で口座が萎む。1〜2%ルールとデビット50%撤退を徹底。
13. 数式の直観(ざっくりでOK)
スプレッド価値 ≈ 期先オプション価値 − 期近オプション価値。期近満期日においては、スプレッド価値 ≈ 残存Tの期先オプション価値に近づきます。よって、ATM性(原資産がストライク近辺に留まる)とIVの平常化が価値を押し上げます。
ギリシャの近似では、θ差>0、net vega>0、gamma<0の組み合わせ。これが「時間は味方・急変は敵」という実務感覚にそのまま一致します。
14. テクニカル×カレンダー:入口の型
- VWAP・出来高帯:当日/週/月VWAPや高出来高ゾーンに近づく→止まりやすい価格にATMストライクを合わせる。
- 移動平均の密集:20/50/100が密集=モメンタム鈍化のサイン。
- レンジ上限・下限のブレーク後の失速:フェイクブレークで中心に戻る読み。
15. 初回の練習メニュー(具体)
- 出来高の多いETFを選ぶ(例:指数ETF)。
- 30D/60Dの限月でATMのコール・カレンダーを1枚だけ建てる。
- デビット(最大損失)を記録し、30〜60%利確/50%損切りのOCO目安をメモ。
- イベント表(決算・政策など)を限月別にメモ。
- 期近満期の5営業日前に撤退判断。延長するならロールの是非を検討。
16. ミニQ&A
Q1:最大利益は? A:理論上、期近満期日にSがストライクぴったり・期先IVが維持/上昇ならピーク。実務は欲張らず分割利確が堅実。
Q2:どちらの権利種別が良い? A:コール/プットは同等。方向の仮説(やや上/やや下)に合わせて選ぶ。
Q3:複数ストライクは? A:慣れたら二山構成(ダブル・カレンダー)で中心帯を広げる手もあるが、初心者は単一ストライク推奨。
17. チェックリスト(発注前の最終確認)
- イベントがどの限月に載るか可視化したか?
- 板の厚さ・スプレッドを確認したか?
- デビット総額=最大損失を理解したか?
- 利確/損切りの数値ルールを書いたか?(30〜60%利確、50%損切)
- 期近満期の5営業日前に撤退判断するか?
18. まとめ
カレンダーは、時間とボラティリティという市場の“構造的な力”を収益化します。デビット限定の損失設計で学びやすく、「走らない相場でコツコツ取る」に極めて向いています。入門のコア戦略として、一度小サイズで反復練習して、自分のルールに落とし込むことを強くおすすめします。

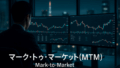

コメント