結論ファースト:カレンダースプレッドは「同一ストライク・異なる満期」を組み合わせ、時間価値の減衰差(シータの差)と期限別IV(ボラティリティ期限構造)の歪みを収益源にするオプション戦略です。価格が大きく動かない相場、または「今は静か・後でやや動く」相場で優位性が出やすく、適切な銘柄・満期ペア・管理ルールを使えば、初心者でも時間を味方につける収益設計が可能です。
1. カレンダースプレッドとは何か
カレンダースプレッド(Calendar Spread)は、同じ権利行使価格(ストライク)で、近い満期のオプションを売り、遠い満期のオプションを買う構成を基本とします。コールでもプットでも成立し、ATM(At‑the‑Money)で組めばデルタは小さく、ベガ(IV感応度)プラス・シータ(時間価値)プラスに寄りやすいのが特徴です。
- ロング・カレンダー:近月売り+遠月買い(一般的)。時間価値の差と遠月IVの粘りに賭ける。
- ショート・カレンダー:近月買い+遠月売り(上級者向け)。ベガがマイナスとなり、IV下落に賭ける構造。
本稿は初学者でも扱いやすいロング・カレンダーにフォーカスします。
2. 優位性が出やすい相場環境
ロング・カレンダーの主な収益源は次の二つです。
- 時間価値の減衰差(シータ差):短期オプションは減価が速く、長期は緩やか。売りの減価>買いの減価となりやすい。
- IV期限構造の形状:通常、遠月IVは近月より高め(コンタンゴ的)。イベントが近い場合は近月が跳ねやすいなど、形状変化(ツイスト)がリスク・機会を生む。
従って、価格は大きく動かず、IVが穏やかな局面で安定収益を狙いやすく、イベント前後は期限構造の歪みで追加の妙味も生じます。
3. 建玉の仕組みとキャッシュフロー
例としてATMコールでロング・カレンダーを構成します。
構成:+ 90日後満期のATMコール(買い)
− 30日後満期のATMコール(売り)
初期コスト:デビット(支払い)になるのが通常
証拠金:ネット買い構造のため比較的軽い(ブローカー仕様に依存)近月売りの時間価値が早く減り、期日到来で消滅すると、遠月のロングだけが残る状態になります。価格が大きく動かなければ、売りの減価獲得 − 買いの減価が純益に寄与します。
4. ギリシャの全体像
- デルタ:ATM付近で小さく、価格方向の賭けになりにくい。必要なら小口の先物や株で微調整。
- ガンマ:概ね小さめ。急な価格変動には強くないため、レンジ外の動きはリスク。
- シータ:近月売りの減価が速いためプラスに寄りやすい(ただし価格が大きく逸れると悪化)。
- ベガ:プラス。IV上昇で有利、IVクラッシュで不利。期限構造のツイストに注意。
5. 価格直観と簡易近似
ロング・カレンダーの価値は、ざっくり遠月オプションの理論価値 − 近月オプションの理論価値。近月の時間価値が速く溶ける分、ポジション価値は時間とともに増えやすい一方、原資産価格がストライクから大きく離れると両者がディープITM/OTM化して価値差が縮みます。
ブレークイーブン帯は厳密計算が必要ですが、近月満期時の原資産価格がストライク近辺であれば利益が出やすい、という直観でOKです。
6. 具体例:数値でイメージを固める
以下はあくまでイメージ用の仮数値です。ストライク=100、原資産=100、金利・配当は無視。
| レッグ | 満期 | IV | 理論価格(例) |
|---|---|---|---|
| 買いコール | 90日 | 22% | 5.20 |
| 売りコール | 30日 | 20% | 2.10 |
初期支払い(デビット)=5.20 − 2.10 = 3.10。
30日後、近月が満期を迎えるタイミングの損益を3パターンで概観します(遠月の残存60日、IVはケース別)。
| ケース | 30日後の原資産 | 近月 | 遠月IV | 遠月理論価値(概算) | 損益(概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| ①レンジ維持 | 100 | 消滅 | 22% | 4.60 | +1.50(4.60 − 3.10) |
| ②上方向にやや離れる | 104 | 消滅 | 21% | 3.70 | +0.60 |
| ③急伸・急落 | 110 or 90 | 消滅 | 23% | 3.20 | +0.10(ほぼトントン) |
レンジ中心で強い一方、極端なトレンドでは優位性が薄れます。IVが想定外に近月だけ跳ねる「期限構造ツイスト」では一時的に逆風もありえます。
7. 銘柄と満期ペアの選定
- 出来高・スプレッド:板が厚く、スプレッドが狭いETFや時価総額の大きい個別株が扱いやすい。
- イベント:決算・経済指標・政策会合が近月に集中すると、近月IVが上振れる。避けるか、意図して組むかを明確に。
- 満期ペア:30日売り×60–90日買いが定番。週次満期(W)を使うと精緻に調整可能。
- ストライク:基本はATM。方向性がある場合はややOTM寄せ(=ダイアゴナルに近づく)。
8. 約定テクニック(コスト最適化)
- スプレッド注文を使い、ミッド(気配の中値)前後で根気よく指値。
- 板の厚い時間帯(現物市場オープン後)を狙う。
- 片レッグだけ先行約定は避け、同時約定を基本にする(スリッページ抑制)。
9. リスクと損切り・ロール
主なリスクは次の通りです。対策をルール化しましょう。
- 価格が大きく離れる(トレンド):デルタ中立の再調整(小口先物/株でヘッジ)か、損切り。レンジ外2σや事前設定の損失額で機械的に実行。
- IVクラッシュ:ベガ+のため逆風。イベント後や急騰相場後のIV均しで段階建てを採用。
- 期限構造ツイスト:近月だけIVが上振れ。近月を一段外側のストライクへロールしてデルタとガンマの歪みを和らげる。
近月満期が近づいたら、ロール(次の近月に乗せ替え)でポジション寿命を延ばす戦略が有効です。利益が乗っていれば、デビット回収率(初期支払いの何%を回収したか)で利確を判断すると客観的です。
10. 応用:ダイアゴナル/ダブル・カレンダー
- ダイアゴナル(斜め):ストライクをずらす。たとえば、やや強気であれば近月売りをOTMコール、遠月買いをATMコールに。
- ダブル・カレンダー:同一満期ペアでコールとプットを同時に構成(ストライクは同距離の±)。レンジの広がりに強くなるが、初期デビットは増える。
11. 実務のチェックリスト
- 板厚・スプレッド・出来高を確認(取引コストが優位性を食わないか)。
- 主要イベントの日付と位置(近月と遠月のどちらにかかるか)。
- 期限構造(近月IVと遠月IVの関係、ツイストの兆候)。
- 初期デビットと目標回収率(例:30–50%で部分利確)。
- レンジ外シナリオの対応(デルタ調整 or クローズ)。
12. よくある失敗
- イベント前の近月IV上振れを軽視:エントリーが不利になりやすい。
- 出来高の薄い銘柄で約定難・スリッページ拡大。
- ロール基準が曖昧で、利を伸ばせない/損を放置。
13. 収益設計の考え方(期待値)
期待値=勝率×平均利益 − 敗率×平均損失。ロング・カレンダーは「小さめのレンジでコツコツ回収」が基本。勝率を上げたいなら、イベント直後の落ち着きを狙う、IVが素直な上昇トレンドでない期間を選ぶなど、環境選別で改善できます。
ポジションサイズは、1回の損失が総資金の1–2%以内に収まるよう逆算しましょう。
14. 実践テンプレ(手順)
- 候補銘柄の板・出来高・スプレッドを確認。
- イベントカレンダーを確認し、近月と遠月の位置関係を把握。
- 満期ペアを選ぶ(例:近月30日×遠月90日)。
- ATMを基本に、必要なら軽く方向バイアス(±1段OTM)を付与。
- ミッド前後でスプレッド注文、約定コストを最小化。
- 日次で原資産の乖離・IV・評価損益をチェック。必要ならデルタ微調整。
- 近月残り7–10営業日でロール判断。回収率に応じて部分利確。
- 想定外のトレンドやIVショックでは、ためらわず撤退。
15. まとめ:時間を味方にする設計
ロング・カレンダーは、「価格は大きく動かず、時間とともに有利になる」という構造的優位を持ちます。板・期限構造・イベント・ロール基準という数点を守るだけで、初心者でも再現性の高い運用が可能です。まずは小さく始め、同じルールを10回・20回繰り返すことで、自分の勝ちパターンを確立しましょう。
応用のヒント:慣れてきたら、ダブル・カレンダーでレンジ耐性を上げる、ダイアゴナルで緩やかなトレンドを取りにいくなど、「時間×方向」の設計自由度を拡張していきましょう。

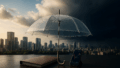

コメント