要旨:本稿では「マーク・トゥ・マーケット(Mark-to-Market, MTM)」の考え方を、株・FX・先物・暗号資産(パーペチュアル先物)の各市場に共通する“評価のルール”として体系的に解説します。初心者でも今日から評価損益の読み方が変わるよう、用語定義から日次清算(デイリー・セトルメント)、証拠金の変動、資金調達率(Funding Rate)、清算価格(Liquidation Price)まで、数式と具体例で丁寧に噛み砕いて説明します。
MTMは単なる会計用語ではありません。トレーダーにとっては「1日の終わりに実際に現金が増減する基準」であり、リスク管理と資金管理の最重要KPIです。評価の付け方が分かれば、同じ値動きでも“生き残るポジション”と“強制終了されるポジション”の差が生まれます。本稿は、評価が現金化されるメカニズムを直視し、相場に長く居続けるための初歩的な実務知識を提供します。
- 1. MTMのコア概念:何を、いつ、いくらで評価するか
- 2. 用語の整理:評価損益・実現損益・証拠金・NAV
- 3. 例①:現物株のMTM(日本株のシンプルなケース)
- 4. 例②:FX(USD/JPY)のMTMとロール・スワップ
- 5. 例③:先物の「日々清算(Variation Margin)」を数値で追う
- 6. 例④:暗号資産パーペチュアルのMTM(マーク価格・Funding・清算価格)
- 7. 「マーク価格」と「最後の取引価格」のズレに注意
- 8. MTMがリスク管理に及ぼす5つの実務インパクト
- 9. 数式ミニガイド:評価・清算・清算価格の概観
- 10. 失敗パターンと回避策:初心者が陥りやすい落とし穴
- 11. 初心者向けチェックリスト(印刷推奨)
- 12. 具体的な練習:エクセル/スプレッドシートでMTMダッシュボードを作る
- 13. ケーススタディ:同じ値動きでも資金管理で結果が変わる
- 14. まとめ:MTMは“生存技術”である
1. MTMのコア概念:何を、いつ、いくらで評価するか
MTMとは、保有資産・負債を「時価(市場価格)」で継続評価し、期中の損益を適切に反映する手続きです。トレーディングでは、約定価格と現在価格の差で未実現損益(評価損益)が生まれ、先物やレバレッジ取引では日々清算により一部(ときに全額)が現金として確定します。重要なポイントは次の3つです。
① 価格基準:終値、清算値、インデックス価格、マーク価格など、取引所・ブローカーが公表する“評価に使う公式価格”。
② タイミング:毎日(先物)、一定間隔(暗号資産の資金調達)、ロールオーバー時(FX/CFD)など。
③ キャッシュ・フロー:先物の変動証拠金やパーペチュアルの資金調達率は、評価と同時に資金移動が発生します。
この3点を押さえると、各市場の“細則”はすべて同じ原理のバリエーションであることが分かります。
2. 用語の整理:評価損益・実現損益・証拠金・NAV
未実現損益(Unrealized P/L)は、ポジションをクローズせずに価格だけが変化した結果の損益です。実現損益(Realized P/L)は、クローズや日々清算で現金として計上された損益を指します。証拠金(Margin)は、ポジション維持のために拘束される担保資金で、MTMにより変動します。ファンドやETFでは、NAV(基準価額)がMTMで日次算出され、投資信託の「今日の理論価値」として公表されます。
3. 例①:現物株のMTM(日本株のシンプルなケース)
前提:A社株を1,000株、1,000円で買付。手数料・税は簡便化のため一旦無視します。
終値が1,030円なら評価益は「(1,030−1,000)×1,000=30,000円」。まだ売っていないため未実現利益ですが、翌日の寄付で売れば実現化します。現物株は通常、日々清算による現金移動はありませんが、評価の把握はポジション管理の出発点です。
ポイントは「評価はあなたの行動(資金繰り)を先回りすべき」ということです。含み損が−10%に接近したら逆指値を置く、含み益が+10%に達したら一部利確する等、評価の閾値を事前に決めておくことで、裁量のブレを抑えられます。
4. 例②:FX(USD/JPY)のMTMとロール・スワップ
FXはレバレッジ取引の代表例で、証拠金評価がクリティカルです。USD/JPYを1ロット(10万通貨)で145.000円ロングしたとします。スプレッドは0.2銭、レバレッジは25倍とします。
評価損益は「(現在レート−建値)×10万」。たとえば146.200になれば+120,000円、143.500なら−150,000円です。この評価は常時変動し、証拠金維持率に反映されます。さらに、日を跨ぐとスワップポイント(金利差調整)が受払され、実現損益に近い形で現金が動きます。
初心者がまず避けるべきは「証拠金の薄張り」です。評価損で維持率が下がると、追加証拠金やロスカットのリスクが急上昇します。想定ボラティリティ×ロット×レバレッジの三点で「最悪ケースのドローダウンに耐えられる現金」を用意してください。
簡易シミュレーション:想定ボラティリティが1日±1.5円、建玉は10万通貨、レバレッジは25倍。1.5円逆行すると評価は−150,000円。口座現金が300,000円なら維持率は急低下し、もう1日分の逆行に耐えられない可能性があります。“2日逆行”に耐える資金を初期から入れておくのが基本です。
5. 例③:先物の「日々清算(Variation Margin)」を数値で追う
先物では、毎営業日、清算値に基づいて評価差額が現金で授受されます(これがMTMの本丸です)。ミニ先物を1枚、建値30,000でロングしたとします(倍率は簡略化)。
1日目清算値が30,400なら+400がその日のうちに口座へ入金、2日目が29,900なら−500が出金されます。値洗いの結果、評価は毎日実現化されるため、損失の先送りができません。この規律が、レバレッジ市場の健全性を担保しています。
トレーダーに必要なのは「清算値ベースでの損益推移表」です。建値やラスト価格ではなく、清算値でキャッシュ増減を積み上げ、必要証拠金と余力の関係を毎日点検しましょう。
6. 例④:暗号資産パーペチュアルのMTM(マーク価格・Funding・清算価格)
暗号資産の無期限先物(パーペチュアル)では、MTMの基準にマーク価格(Mark Price)が使われることが多く、清算判定や評価に直接影響します。また、一定間隔で資金調達率(Funding Rate)の授受が発生します。これは先物のベーシスをスポットに近づけるためのメカニズムです。
清算価格の直観:たとえば証拠金1,000USDT、レバレッジ10倍でBTCをロング。ポジション名目は10,000USDT。維持証拠金率が0.5%なら必要維持額は50USDT。手数料等を無視すれば、「評価損が1,000−50=950USDTに達した時点」で清算されます。マーク価格がこの閾値に触れたら終了です。
Fundingの影響:ロング優勢の市況では資金調達率がプラスになり、ロングがショートに支払い、逆相場では受け取ります。これはキャリー(保有コスト)であり、クローズせずとも実現損益として財布に反映されます。資金管理上は、価格P/LとFunding P/Lを別トラックで集計し、通算のキャッシュフローを監視してください。
7. 「マーク価格」と「最後の取引価格」のズレに注意
清算や証拠金評価には、板の薄さや一時的なスパイクの影響を平滑化するため、取引所が算出するマーク価格(指数連動・移動平均等)が使われます。あなたが見ている“現在値”でなく、マーク価格がルールの基準かもしれません。約款を読み、どの価格が評価・清算のトリガーになるかを必ず確認しましょう。
8. MTMがリスク管理に及ぼす5つの実務インパクト
① 損失の前倒し認識:先物やパーペチュアルでは不利な日に現金が流出します。ドローダウン耐性は「日次キャッシュアウト前提」で見積もる必要があります。
② 資金繰りとレバレッジ上限:理論上の最大損失ではなく、日々の必要現金でレバレッジ上限を逆算します。
③ 逆行時の行動ルール:清算価格に近づいたら追加入金か縮小か、意思決定の優先手順を事前に定めます。
④ ヘッジのタイミング:ベータ抑制のヘッジは、清算値発表前後の流動性とスプレッドでコスト最小化を図ります。
⑤ 戦略評価:バックテストでは「価格P/L」だけでなく、Fundingやスワップの累積を別勘定で足し込み、現金ベースのリターン曲線を確認します。
9. 数式ミニガイド:評価・清算・清算価格の概観
未実現P/L(現物・FX):Unrealized = (P_t − P_0) × 取引数量
日々清算(先物):Variation = (Settlement_t − Settlement_{t−1}) × 取引数量
パーペチュアルFunding:Funding P/L = 名目 × Funding Rate × 保有時間比
清算価格の簡易近似(クロスでない単独証拠金):Liquidation ≒ 建値 − (証拠金 − 維持証拠金) / 名目数量(ロングの場合)。取引所の仕様・手数料・バッファで実値は変わるため、約款計算式を必ず確認してください。
10. 失敗パターンと回避策:初心者が陥りやすい落とし穴
① 「評価=現金」と誤解する:未実現益を前提にポジションを増やすと、反転一撃でロスカット連鎖に繋がります。
② 清算値の無視:先物で終値だけ見ていると、実際の出金額と合わず資金管理が破綻します。
③ Fundingを見落とす:強気相場でのロングは受け取りで有利ですが、相場転換で支払いに変わると長期保有コストが膨らみます。
④ 板薄・スリッページ:清算価格に近い状況での成行は、実効損失を増幅させます。
⑤ クロスマージン依存:複数ポジションの相殺は便利ですが、相関が崩れた瞬間に一斉清算の危険があります。
11. 初心者向けチェックリスト(印刷推奨)
・自分の取引所/ブローカーの「評価基準価格」は何か(終値・清算値・インデックス・マーク価格)。
・先物/パーペチュアルの「日々清算時刻」「Funding時刻」と授受の方法。
・口座の「維持証拠金率」「証拠金の種類(クロス/アイソレ)」と清算価格の計算式。
・「2日連続の最大逆行」に耐えられる現金余力(現金・追加入金可否)。
・損切りと縮小の優先順位(どのポジションから削るか)。
・Fundingやスワップを別勘定で記録しているか。
・清算値ベースの損益推移表を毎日更新しているか。
12. 具体的な練習:エクセル/スプレッドシートでMTMダッシュボードを作る
① 価格入力:建値、現在値、終値/清算値、マーク価格、スワップ/Funding、手数料を列に分けます。
② P/L分解:価格起因のP/L、日々清算、Funding/スワップ、手数料を別列で算出し、合計=キャッシュの増減に一致させます。
③ 余力・清算距離:維持率、清算価格までの距離(%・金額)を常時計算。
④ 閾値アラート:距離が一定以下でセルを赤くする条件付き書式を設定します。
⑤ 日次レビュー:清算値反映後に“何が現金で動いたか”を一行でメモします。
この“可視化”は、裁量に依存した危険な意思決定を防ぎ、再現性のあるトレードに近づけます。
13. ケーススタディ:同じ値動きでも資金管理で結果が変わる
ケースA(薄い証拠金):BTCロング、名目10,000USDT、証拠金1,000USDT、Funding支払い年率10%相当。−6%逆行で清算価格接近、Funding支払いも重なり強制ロスカット。
ケースB(厚い証拠金):同条件で証拠金3,000USDT。−10%逆行でも清算を回避し、反発+8%で回収。Fundingコストは発生するが、時間を買う選択ができる。
この差は「相場観」ではなく「MTMとキャッシュフローの設計」です。初心者ほど、まず厚めの余力から始め、清算価格が遠い環境で練習してください。
14. まとめ:MTMは“生存技術”である
相場に長く居続けるためには、価格の当て勘よりも、評価が現金に変わる瞬間を正しく知ることが大切です。MTMはその地図です。自分の市場の評価ルール(価格基準・タイミング・キャッシュフロー)を把握し、清算価格に近づかない資金設計と、価格P/LとFunding/スワップを分解した記録を、今日から始めてください。

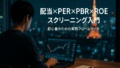

コメント