本稿では、暗号資産の「オンチェーン分析」を、個人投資家が現実の売買判断に落とし込むための実戦フレームワークとして体系化します。テクニカル分析(価格と出来高)でも、ファンダメンタルズ(プロジェクトや財務)でもなく、ブロックチェーン上で実際に発生したトランザクションや残高変化という「事実」に基づいて、市場参加者の行動と資金循環を読み解きます。対象はビットコイン、イーサリアム、主要アルトコイン全般です。初学者でも運用に載せられるよう、データ選定→指標化→合成→ルール化→検証→運用の順で解説します。
オンチェーン分析とは何か:位置づけと射程
オンチェーン分析は、ネットワークの利用状況と資金の出入りを、アドレス単位・コホート単位で観測する手法です。株式で言うところの「需給の中身」を直接見るイメージです。価格は結果であり、オンチェーンは原因側の一部です。具体的には、アクティブアドレス、トランザクション数、手数料/ガス、保有期間別の供給、取引所への資金フロー、ステーブルコイン供給、マイナー/バリデータの売り圧、ステーキング比率などを観測します。
取得するデータの全体像:どの層を見ればいいか
最初から全てを追う必要はありません。以下のレイヤー順に絞り込みます。
レイヤー1:需給の直接指標
①取引所残高とネットフロー(Exchange Balance/Netflow):現物の売り玉が増減しているか。②ステーブルコイン供給とエクスチェンジ進出量:新規の購買余力が増減しているか。③大口(クジラ)・小口(リテール)の保有量変化:誰が買って誰が売っているか。
レイヤー2:利用度と混雑
①アクティブアドレス数と新規アドレス数、②トランザクション数とメンプール滞留、③手数料/ガス価格:ネットワークの実需や熱狂の度合いを示します。
レイヤー3:保有構造と含み益・損
①MVRV/NUPL(評価益/損の分布)、②SOPR(売却時の損益比)、③HODL Waves/UTXO年齢帯:売り圧/買い圧の背景を読み解きます。
レイヤー4:コンセンサス供給源
ビットコインならハッシュレート/難易度、イーサリアムならステーキング比率・バリデータ入退出・ガスバーン。供給のネット変化とセキュリティコストを観ます。
主要KPIの読み方と閾値設計
取引所残高・ネットフロー
現物の「売れる在庫」は取引所にあります。ネットフロー(取引所への純入金)が継続してプラスなら潜在的な売り圧増、マイナスなら引き出し=保管志向の強まりで売り圧低下と解釈します。閾値は「30日移動平均で±2σ」を目安に極端判定を行い、極端な流入は短期の上値重さ、極端な流出は中期の下値堅さと関連付けます。
ステーブルコイン供給・為替進出
USDT/USDCなどの供給伸び率と、取引所アドレスに入るステーブルの量は「新規ドライパウダー」です。供給YoYが鈍化/縮小する局面では中期の上昇持続性が落ちやすく、逆に供給拡大は押し目の買い支えになりやすい。短期は「取引所進出の急増→近い日の現物買い→数日遅行」という時差も見ます。
MVRV / NUPL
MVRVは時価総額/実現時価総額で、平均コストに対する含み益倍率の概念です。過度な高水準は利確圧力が高まりやすく、低水準は売られ過ぎでリバウンド余地が生まれます。NUPLはネット未実現損益の比率で、感情状態(恐怖/楽観)を推定するのに使えます。絶対値の「魔法の数」は存在しないため、各銘柄の分布に合わせて分位点(上位20%、下位20%など)で閾値化するのが実務的です。
SOPR(Spent Output Profit Ratio)
売却時が平均して利食いか損切りかを示します。1を跨ぐ転換が起点になりやすく、特に「1を下から上へ抜けて定着」は上昇の質改善、「上から下へ割り込んで定着」はトレンド悪化を示唆します。ノイズを抑えるため7〜14日の平滑化が有効です。
アクティブアドレス・新規アドレス
成長トレンドでは双方が滑らかに増加します。価格急騰だけが先行し、ユーザー指標が伸びない場合は投機主導で続きにくい。移動平均のゴールデンクロス/デッドクロスを補助線にします。
手数料/ガス・メンプール
ユースケースの活性(NFT/DeFi/ミーム波)で手数料上昇→短期の過熱と中期のネットワーク価値上昇の両面があります。異常高騰は短期利確のきっかけにもなります。
ハッシュレート/難易度・ステーキング比率
BTCのハッシュレート上昇と難易度の堅調は、セキュリティの強化とマイナーの設備投資意欲を反映します。一方でマイナーの売却(採掘したBTCのエクスチェンジ送金)が増えると局所的な売り圧になり得ます。ETHではステーキング比率の上昇が流通供給のロックアップを通じて下値を支える一方、アンボンド解放期はフロー的に短期の重しになることがあります。
複合スコアで「買い/様子見/警戒」を判定する
単一指標の過信は危険です。互いに独立性のある指標を選び、スコア合成で意思決定します。例として、以下7指標に0〜2点を付与して合計します(最大14点)。
①取引所ネットフロー(流出=+2, 中立=+1, 流入=-2)②ステーブル供給伸び(拡大=+2, 横ばい=+1, 縮小=-2)③MVRV分位(下位20%=+2, 中位=+1, 上位20%=-2)④SOPRの位置(1超で上向き定着=+2, 1付近=+1, 1割れ定着=-2)⑤アクティブ/新規アドレスMA(上向き=+2, 横ばい=+1, 低下=-2)⑥手数料/ガス(適温=+1, 過熱=-1, 低迷=-1)⑦ハッシュ/ステーク(改善=+1, 悪化=-1, 中立=0)。
合計が+6以上なら「押し目買いを検討」、0〜+5は「様子見/スイング限定」、-1以下は「現金比率を高める」。この域値は戦略のボラ耐性に合わせて調整します。
売買ルール:実装テンプレート
エントリー
ルールA:複合スコアが+6以上、かつSOPRが1超で5日定着、かつ取引所ネットフローの7日MAがマイナス継続。この3条件を満たした日の翌日始値で1単位エントリー。
エグジット
①複合スコアが+2未満に低下、または②MVRVが上位20%帯に進入、または③手数料/ガス急騰(分位80%以上)+価格が2日連続で上髭長い陰線。このいずれかで半分利確、2つ同時なら全利確。
リスク管理とサイズ
資金の2%ルール(1トレードの最大損失を総資金の2%以内)を適用。ATRや直近スイング安値を初期ストップに置き、利益確定後は建値+αにストップを切り上げます。複数銘柄同時エントリー時は相関を考慮し、合計リスクを4%以内に制限します。
戦術パターン:資金循環・イベント・清算
資金循環マップ
ステーブル供給増→BTC→ETH→大型アルト→小型アルトの順に波及することが多い。オンチェーンでは「取引所のステーブル進出が先→BTC現物引き出し→ETHのガス/バーン増→DEX流動性増→小型に波及」という時系列で確認できます。循環の前工程が走り始めたら、後工程の押し目で仕込みます。
イベント駆動
ハードフォーク、ETF関連、ハルビングなどの材料は、オンチェーンの先行変化(開発者・バリデータの動き、ステーキング比率、手数料急騰)として現れることがあります。価格より先に「利用と資金」が動くケースを待ち伏せします。
清算ヒートマップの活用
先物の清算クラスター近辺で出来高が吹き上がるとき、取引所流入が急増していると上値が重くなりやすい。逆に流出が続く中で清算が出る時は、踏み上げ相場への燃料になりやすい。オンチェーンとデリバティブの一致/不一致でシナリオ分岐を描きます。
ケーススタディ(仮想データ例)
想定:BTCで、①取引所ネットフロー7日MAが-8,000BTC/日、②USDT総供給が前月比+3%、③MVRVが分位35%、④SOPRが1.01で10日定着、⑤アクティブアドレスMAが上向き、⑥手数料は過熱でも低迷でもない、⑦ハッシュレート上昇。このとき複合スコアは概ね+7〜+8。翌日から分割3回で現物を買い下がり、ストップは直近安値-2ATR。価格が実現時価総額の+1σを明確に上抜けば残りも追加し、MVRVが上位20%帯入りで半分利確、SOPRが1割れで残りも手仕舞いとします。
簡易バックテスト:表計算で十分始められる
①日次の価格・出来高、②取引所ネットフロー7日MA、③ステーブル供給月次変化、④MVRV分位、⑤SOPR、⑥アクティブアドレスMA、⑦手数料分位、⑧ハッシュ/ステークのダミー変数(改善=1/悪化=-1)を列に用意。IF文で各スコア(-2〜+2)を算出し合計→売買ルールに従いシグナルを生成します。損益は=IF(エントリー, 翌日始値, 前回価格)の差分で計算、手数料・スリッページを毎取引0.10%〜0.20%控除。評価指標はCAGR、最大ドローダウン、勝率、平均損益R、シャープ/ソルティノ、プロフィットファクター。期間を牛/熊/レンジに分けてロバスト性を確認します。
リスク管理:価格より「フローの断絶」を恐れる
①取引所やブリッジの停止・破綻、②ステーブルコインのペッグ外れ、③チェーンの混雑・手数料高騰で約定不能、④データ配信遅延や欠損、⑤アドレスクラスタリング誤り(ラベルの誤特定)など、フローの断絶は想定外のギャップ損を生みます。分散保管、複数取引所・複数ステーブルの併用、成行偏重の回避、バックアップデータ源の確保で耐性を上げます。
よくある誤解と落とし穴
・「クジラが買えば必ず上がる」:クジラ同士が反対売買していることも多い。買いフローは現物引き出しの伴走で信頼度が上がる。
・「MVRV = 〇〇なら売り」:単純閾値は時期や銘柄で変動。分位点と他指標の同時確認が前提。
・「アクティブアドレス=ユーザー数」:ボットや分散送金で水増しされ得る。新規/休眠復活の比率で質を担保。
・「手数料高騰=弱気」:短期過熱と中期価値増の二面。価格文脈と併読する。
・「オンチェーン万能」:オフチェーン要因(規制/会計/税制/流動性供給)が価格に与える影響は依然大きい。
実装チェックリスト
□ 7指標のダッシュボード化(分位点とMA表示)/□ スコア自動計算とログ保存/□ 日次の定時レビュー(15分以内)/□ 2%ルールの徹底/□ 相関管理(銘柄横断で同時リスク過多を避ける)/□ 例外ルール(清算急増・メンプール異常・ステーブル急変時の一時停止)。
まとめ
オンチェーン分析は、価格の背後で動く「人と資金」の流れを可視化する技術です。単一の魔法指標に頼らず、独立性のある複数KPIを分位点で正規化し、複合スコアで売買ルールに翻訳する。小さく始め、ログを積み上げ、バックテストと前向き運用を往復させれば、裁量にもシステムにも馴染む堅実な土台になります。


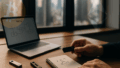
コメント